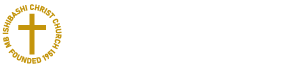テモテへの手紙第一 5:17ー25
礼拝メッセージ 2025.2.23 日曜礼拝 牧師:太田真実子
本日の聖書箇所では、①長老は十分な報酬(長老への尊敬)を受けるべきこと(17-18節)と、②長老への訴え(19-25節)について、扱われています。私たちはこれらの勧めの意図をよく理解し、祈りをもって、主のみこころを行う者とならせていただきましょう。
1,教職者が十分な報酬を受けられるように(17-18節)
当時、「監督」と「長老」とは同じ人々で、教会の「監督(見張る人)」の職についた人が年配であることが多かったことから、「長老」とも呼んでいたようです。長老は教会の兄姉たちを指導する責任がありました。「尊敬を受ける(17節)」とは「値段(マタイ27:9)」や「報酬」とも訳される語です。ですから、「尊敬」という少し抽象的な思い以上に、尊敬からくる長老の職務に対する謝礼や報酬に対して述べられていると読むこともできます。「二倍の報酬(尊敬)を受けるにふさわしいとしなさい(17節)」とは、他者との比較において言われているというよりも、監督職に就く者が十分な謝礼や報酬を受けることができるための命令と理解すべきでしょう。
一方で、3章3節では監督の職に就く者の資格について「金銭に無欲」であることが挙げられていることにも注目したいと思います。つまり、手紙の筆者は、監督職に就く者が他の人々よりも裕福になることを願っているのではありません。ただ、彼らが金銭的に貧困であって良いとは考えていないということです。多くの教会の教職者たちが金銭面で苦労していることは、今の日本においても言えることでしょう。私たちは、キリストの教会の働き人について、「彼らは金銭に無欲であるべきなので、低賃金であるべき」と考えないようにしましょう。主の働き人に対して尊敬の思いを抱き、衣食住においても十分な主の恵みが受けられるようにしましょう。
手紙の筆者は、聖書のみことばを根拠にして、このことを訴えています。「脱穀をしている牛に口籠をはめてはならない(申25:4)」のは、穀物をこなしている牛が床にこぼれた穀物を自由に食べることができるようにするためです。そして、「働く者が報酬を受けるのは当然である(ルカ10:7)」はイエス様のことばです。これらはのみことばには「働く者が十分な報酬を受けるべき」ことの説得力があります。
また、「十分に受けるべき」という点においては、教会の教職者だけが該当する問題ではありません。主に造られたすべての人が、主の恵みを十分に受けることができるように、私たちは恵みを分かち合っていくべきです。
2, 自分を清く保ちなさい(19-25節)
次に、長老への訴えの問題が述べられています。あらゆる組織に言えることかもしれませんが、管理職という立場は、誤解や偏見も受けやすいものです。だからこそ、そのような立場にある人への訴えは特に慎重であるべきです。ただ、これは長老のみに当てはまる特別な規則と考えるべきではありません。申命記19章15節自体もそうですし、イエス様ご自身も兄弟たちに証人は2〜3名であることを勧めておられます(マタイ18:16)。要するに、このことは一般の人に対してもそうであるべきことですが、長老に対しては特に注意しなさい、ということでしょう。
長老に関する記述は19節で終えられていると理解される場合もありますが、22節で按手について触れられているため、20節以降も長老に関する内容が続いていると理解していきたいと思います。
そうであるならば、20節の「罪を犯している者」とは「罪を犯し続けている者(原文)」なので、ここでは「罪を悔い改めていない長老」に関する命令だと言えます。長老が罪を犯したかどうかは慎重に審議されるべきですが、もしそうであるなら、教会の兄姉たちの前でも明らかにされるべきだということでしょう。教会の監督の罪を曖昧にするならば、教会の兄姉たちの間に不信感を募らせ、キリストの教会の一致を破壊させてしまうことになりかねません。キリストをかしらとした教会の監督職だからこそ、人々の前で責められるべきです。
そして、これらのことは、関係性によってえこひいきせずに、主がご覧になっておられることを覚えながら、行われるべきです(21節)。性急な案集を禁じているのは、長老(監督職)に就いている者の罪が教会に与える影響は深刻だからです(22節)。按手をした側の責任も問われることになるでしょう。
それから、手紙の筆者は「自分を清く保ちなさい」と言います(22節)。自分が清く正しく生きることは、教会に良い一致を与えます。見かけばかりの「清さ」は、主の御前に隠し通すことができません(25節)。さばきのときには、良い行いも悪い行いも、明らかにされます。ただ、そのさばきは、私たちを永遠の滅びに向かわせるものではありません。私たちは恵みによって永遠のいのちが与えられています。恐れなくて良いのです。主は、「みこころが天で行われるように、地でも行われ」ることを望んでおられます。恵みによって救われているからこそ、やがて主に「よくやった」とおっしゃっていただけるよう、良い行いに励んでまいりましょう。