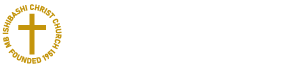ヘブル人への手紙 4:1ー13
礼拝メッセージ 2025.4.13 日曜礼拝 牧師:船橋 誠
1,恐れようではないか、安息に入れない人が出ないように
みことばが信仰によって結びつけられなかった
「私たちは恐れる心を持とうではありませんか」(1節)と著者は語りかけます。直訳すれば、「私たちは恐れようではないか」となります。聖書の約束の多くは、たいてい「恐れるな」であるはずなのに、ここでは珍しく私たちに向かって、「恐れようではないか」と迫っています。では、その恐れる必要のあることとは何でしょうか。それが「神の安息に入るための約束がまだ残っているのに、あなたがたのうちのだれかが、そこに入れなかったということのないように」と書いています。第一に、私たちが恐れるべきこととは、神の安息に入れない人が出ないようにするということです。
前の箇所3章7節から19節に書いてあったのは、出エジプトを果たした主の民が、四十年間、荒野を旅して、その多くが約束の地に入れなかったということでした。出エジプト記や民数記などに記されていたとおり、彼らの神への不従順と反抗がそのおもな原因でした。その歴史的教訓をもって、ヘブル書の著者は「恐れようではないか」、「御声を聞くなら、心を頑なにするな」と、読者に語りかけています。
2節には、彼らも「良い知らせ」あるいは「福音」を聞いていたのですが、それが「信仰によって結びつけられなかった」ために、彼らにとってそれが益とならなかったという恐るべき事実を伝えています。彼らが聞いた「良い知らせ」とは、出エジプト記19章3節から6節などに記されているように、彼らをエジプトから解放された神が、約束の地へと彼らを導き、そこを所有させ、彼らを「祭司の王国、聖なる国民」とするということでした。救いの知識や情報は大切なものですが、それを真剣に受け取らず、聞き流し、無視したり、破棄してしまうならば、その恵みを享受することはできないのです。「みことばが、聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかった」ならば、みことばの約束を受けられないのです。
神の安息への招待
3節にあるように「信じた私たちは安息に入る」ことは間違いありません。ここで「安息」と訳されているギリシア語のカタパウシスという単語は、「何かしていることをやめさせる」という動詞のカタパウオーから来ています。そこから、「休息」、「安らぐこと」、「憩い」という意味になりました。この「安息」が究極において約束していることは、労働や仕事など、努力することがもはや終わり、その必要がなくなることなのです。
神の完全な安息は、無償の恵みであり、私たちを悩ませるもの、邪魔するものから完全に解放されて自由になり、心配させるものも、苛立たせるものも何も存在しなくなるのです。心は静まり、落ち着き、平安を得ます。神が永遠の愛をもって私たちを抱きしめてくださっていることを味わうことができるのです。
ですから、神のご用意くださる安息の約束の招きを拒んではいけないのです。ルカの福音書14章15節から24節のたとえ話を思い起こしました。宴会を催した主人がしもべを遣わして、招待している人たちを呼びに行かせます。遣わされたしもべは主人のことばを伝えます。「さあ、おいでください。もう用意ができましたから」と。ところが招待された人たちは、みないろいろな理由をつけて招待を断ります。「畑を買ったので…、牛を買ったので…、結婚したので…」と彼らの拒絶に対して、主人は怒りを燃やしました。ヘブル書に戻ると、4章3節と4節には、天地創造の時に、神が第七日目にすべてのわざを終えて休まれて以降、安息が始まっており、安息に入るように、人々が招かれていることが記されています。そしてモーセの時代を経て、ヨシュアが民を率いて入った約束の地が、地上においての安息であることを示唆しています。しかし、それは究極的な完全な安息ではありませんでした。ダビデが王として治めた王国でさえも、それは完全な安息を民に与えたわけではありません。真の安息は、イエス・キリストによってもたらされました。神は、主イエスを通してすべての人たちに、神の安息を与えようとされています。ですから、ここにその安息がまだ残されていることを著者は強調しています(1、6、9節)。
神のみわざは完了した
3節には、この安息は「すでに成し遂げられた」ものと言われています。十字架の上で主イエスは七つのことばを語られましたが、六番目のことばとされているのが、ヨハネの福音書19章30節にある『完了した』というみことばです。主イエスが地上生涯を歩まれ、そして最後には十字架にかかられて、救いの御業は完了したのです。主が成すべきことはすでに全うされたのです。私たちを罪から贖い、赦しを与え、神の子どもとするという、神の救いの安息は、ここに完了したのです。神は「今日」と仰られます。「さあ来なさい。用意はできました」と。この安息への招待を受けることは今はだれでも可能です。安息に入るための約束はまだ残っています。決して遅すぎるということはありません。神に応答できる状態にあれば、生きている時間内であるならば、その招待を受け取ることができるのです。信じて、神の安息の中に入れるのです。「すべて疲れた人、重荷を負っている人はわたしのもとに来なさい。わたしがあなたがたを休ませてあげます。」(マタイ11:28)とイエスはあなたを神の安息へと招いておられます。今日、もし御声を聞くなら、心を頑なにせず、主を信じましょう。
2,恐れようではないか、神のことばの力を
第二に、12節と13節を見ると、私たちが正しく恐れて歩んでいくために、大事なことは「神のことば」の光に照らされ生きることであるということです。みことばは蜜のように甘く、私たちの渇いた心に潤いを与え、慰めと力を与えてくれるものですが、ここでは、「生きていて、力があり、両刃の剣よりも鋭い」ものとして、言わば危険なものとして描かれます。刀とかナイフは、危険なものですが、日々の生活にとって必要な道具です。そしてまた、鋭利な刃物であればあるほど、切れたことに気づかないほどの切れ味を見せます。神のことばもそうです。私たちが気づかぬうちに、心の奥底に侵入し、思っていることの動機や意図をバッサリと切り分けてしまいます。そういう意味では、正しく聖書を読むことは怖いことです。しかし、同時にそういう神のことばの真の力に接していないなら、それもまた危険なことです。みことばによって、だれにも知られていないこと、また自分でも意識していなかったほんとうの心の内にある思いが刺し貫かれ、さらけ出されてしまうのです。13節にあるように、神のことばを真っ直ぐに受け取ることが、神の御前に出ることにそのまま繋がっています。みことばによって、私たちは心探られ、調べられ、試されることになるのです(参照 詩篇105:19、119:105、139:23−24)。