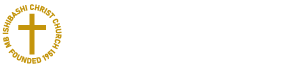ヘブル人への手紙 8:1ー13
礼拝メッセージ 2025.6.22 日曜礼拝 牧師:船橋 誠
1,イエス・キリストの高挙(1〜6節)
イエスさまは、なぜ天に昇られたのか
使徒信条の中に「天に昇り、全能の父なる神の右に坐したまへり…」と言う一文がありますが、イエスさまが十字架にかかられ、死んで葬られて、三日後に復活された後、天に昇られていったことを記憶しておられるでしょうか。ルカの福音書や使徒の働きの中に、そのときの様子が描かれています。
たとえば、ルカの福音書24章51節「そして、祝福しながら彼らから離れて行き、天に上げられた。」とあります。また、使徒の働き1章9節に「こう言ってから、イエスは使徒たちが見ている間に上げられた。そして雲がイエスを包み、彼らの目には見えなくなった。」と記されています。これを一般に「高挙」(こうきょ)と呼んでいますが、もしかすると、イエスさまの救いの御業として十字架と復活にのみ目がいき、この高挙のことについてはあまり大切なこととして見ていなかった方もおられるかもしれません。
しかしヘブル人への手紙の著者は、特にこのイエスの高挙について、読者に目を留めるように勧め、その恵みを語っています。8章1節から2節を見ましょう。「以上述べてきたことの要点は、私たちにはこのような大祭司がおられるということです。この方は天におられる大いなる方の御座の右に座し、人間によってではなく、主によって設けられた、まことの幕屋、聖所で仕えておられます」。なぜ、イエスさまは天に昇られることが必要だったのでしょうか。それはヘブル人への手紙を読めば明らかですが、主は父のみもとへ行き、そこで大祭司として私たちのためにご奉仕くださるためだったのです。
天における真の幕屋
救いのためには罪の赦しが必要です。そしてその罪の赦しのためには、幕屋において祭司がいけにえを捧げる儀式が旧約時代は必要なことでした。幕屋や神殿という「場所」、祭司の役割をする「人」、いけにえという「もの」(内容)が不可欠でした。今日の箇所では、この場所、人、モノという三要件の中で、「場所」に対することが述べられています。それは「幕屋」です。
この書が記された時代は、紀元60年後半と推定されていますから、まだエルサレムには神殿があり、そこで祭司がいて、いけにえや供え物が捧げられる儀式が行われていました。4節に「もしこの方が地上におられたなら、祭司であることは決してなかったでしょう。律法にしたがってささげ物をする祭司たちがいるからです」と記しています。ここに「律法にしたがってささげ物をする祭司たちがいる」と現在形の表現でその時代をありのままに語っています。
けれども、その神殿やかつてモーセの時代に作られた幕屋という場所も、そこで行われている犠牲を捧げる儀式は、5節にあるように「天にあるものの写しと影」にすぎないと著者は言います。「もっと偉大で、もっと完全な幕屋」(9:11)があり、それは天にあるということ、それこそが「まことの幕屋、聖所」(8:2)であるのです。
天にあるのが本体であり、地上に存在するものはその写しと影にすぎないという見方は、ギリシア哲学のイデア論を思い出しますが、聖書はそういう二つの世界に分けて考えること(いわゆる二元論的見方)を教えているのではないようです。むしろ天に上られて目には見えないイエス・キリストが、今現在も大祭司としておられるという重要な真理を伝えるためにこのことを書いているのです。
1節から6節に記されているように、イエスさまが地上におられるときは、ユダ族に属しておられたので、祭司や大祭司として神殿の中でいけにえを捧げるという奉仕をされることはありませんでした。しかし、十字架と復活の御業をなされた後、昇天されたイエスさまは、真の幕屋、聖所に入って、大祭司としてのご奉仕をささげてくださっているのです。1節に戻ってみると、私たちの大祭司であるイエスさまは「大いなる方の御座の右に座し」ていると書いています。これはとても興味深い記述です。地上での幕屋や神殿で、大祭司は祭壇で立ったままで奉仕したのです。大祭司が座るための椅子は備えられていませんでした。祭司たちが座ることがなかったのは、彼らの仕事が決して終わることのないものだったことを示しています。しかし、イエスさまが犠牲を捧げた時、天に上って行かれたとき、父なる神の右に座りました。なぜなら、イエスさまの仕事は完了しているので、座る資格があったからです。主は、ご自身の犠牲という一つのいけにえによって、その御業を成し遂げられたのです。君主の右の座は、名誉や権威を象徴しています。
2,新しい契約(7〜13節)
さて、この章の7節からは「新しい契約」ということについて、10章に至るまでそのことを念頭に著者は語っていきます。ここでエレミヤ書31章31節から34節までの長い引用をしています。「初めの契約」つまり、古い以前の契約、旧約聖書というときの「旧約」と言い換えても良いでしょう。しかし、それと対比されているのが「第二の契約」、すなわち「新しい契約」です。7節と8節に書いているように、初めの契約は良いもので、素晴らしいものでありました。しかし、二つの点において「欠け」(欠点)がありました。それは契約そのものに欠けがあること、そしてそれを受け取る父祖たちに欠けがありました。
これはたとえばこの世界に存在する、多くの道徳的な教えや、人生に役立つ指針などに見ることができることかもしれません。それらが教えていることは高尚であり立派なことですし、そのとおりに歩むことができれば、ほんとうに良いのですが、なかなかそういうふうにはなりません。どうして理想通りにいかないかと考えると、その教えそのものに宿る力がないこと、またその教えを受取る人の側に弱さや限界があるからです。
しかし、10節をご覧ください。新しい契約は、「わたしの律法を彼らの思いの中に置き、彼らの心に書き記す。」と書いてあり、さらに11節には、「主を知れと言って教えることはない。彼らがみな、…わたしを知るようになるからだ。」と告げています。なんと、素晴らしい恵みでしょうか。新しい契約は、神と人との関係を全く別の根底の上に置いてくれます。その根底とは、神ご自身が人間を内的に変化させ、神のご意志が人間の心の奥底を支配し、神ご自身が私たち一人ひとりを、神の本質の本来的な認識で満たしてくれるという約束です。12章2節に「信仰の創始者であり完成者であるイエス」とありますが、私たちの信仰は私たちが完成させるのではなく、イエスさまです。まさに、神さまがこの驚くべき新しい契約で語っていることはそういうことです。私たちの心の中にダイレクトに書き込みをしてくださらないかぎり、私たちの信仰の完成はあり得ないのです。