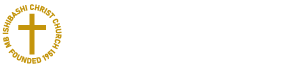ヘブル人への手紙 2:1ー9
礼拝メッセージ 2025.3.2 日曜礼拝 牧師:船橋 誠
1,押し流されてはならない!
危機的状況下で救いを拒む人たち
4節までは一言で言えば「第一の警告」にあたる箇所です。その後も、3章から4章、5章11節から6章20節、10章19節から39節、12章と計五回の警告のことばがこの書にありますが、ここはその最初のものです。ヘブル書の著者は説明しながら、時々立ち止まり、「だから、みなさん、注意してください」と勧告します。それでは、何に、どのように注意するよう語っているのでしょうか。
こんな話を読みました。そびえ立つ断崖絶壁の中腹で降りることも登ることもできず、立ち往生している一人のクリスチャン男性がいます。数十メートル下には、多くの岩石があり、そこを絶えず激しい波が押し寄せる海が広がっています。絶体絶命のピンチです。彼は神に熱心に救いを求めて祈りました。すると、突然、巨大な鷲が現れて男性に近づき、その背中に乗るように促しました。しかし、彼はそれを拒否しました。しばらくすると、ヘリコプターが近づいて来ましたが、彼は手を振って追い払います。その後、小型飛行機が旋回をして、ロープの梯子を降ろそうとしますが、それも断りました。そして彼は祈り続けました。「主よ、なぜ私を救ってくださらないのですか」。すると神は答えました。「わたしはあなたに鳥と、ヘリコプターと、梯子を送ったのに、なぜそれを使わなかったのですか」と。
たいへん奇妙で愚かな話ですが、この話が伝えていることは、神は必ずしも人がイメージしているかたちで、救いの手を差し伸べるのではないということです。確かに神は祈りに応えてくださいますが、それはいつも私たちが期待するかたちであるとは限らないのです。神は常に劇的で超自然的な奇跡でそれに応えられる訳ではなく、しばしば自然な出来事のように見えるかたちで私たちを救い出されます。ヘブル書がここで問題にしていることは、この手紙の宛先の人々は、神がすでに憐れみの御手を差し伸ばしているのに、彼らがそれは違うと思い、救いを拒絶し、その身を危険にさらしているということです。
押し流される危険
この危機的状況を放置するとどうなるかを、ヘブル書の語り手は「このままだと押し流されるよ」と注意します。この「押し流される」(ギリシア語:パラレオー)ということばは、新約聖書でここだけに出てくる独特な表現です。織田昭編『新約聖書ギリシア語辞典』では、「(恵みから漂流して滅びへ)押し流される」という解説がありました。ここで著者が使っている表現は、船やボートのイメージです。船が岸から離れ、安全に港に着くために注意深く舵を取る必要があり、それを怠るなら、間違った方向に流され、漂流することになるという比喩表現を使った警告です。
私たちの信仰について考えると、ここで注意されているように、決して押し流されるままにしてはならないということです。祈ることも、考えることも、大切なことを他人任せにして、ただ流されるままに生きていくことはたいへん危険なことです。世のあり方に押し流されないように、肉の思いに押し流されないように、悪魔の声に押し流されないように、注意しましょう。
19世紀のイギリスの探検家ウィリアム・エドワード・パリーが乗組員たちを率いて北極海へ向かいました。彼らが目指していたのはさらに北へ進んで測量作業を続けることでした。星の位置から現在地を割り出して、非常に困難で危険な北への行軍を続けていたのです。一行は何時間も歩き続け、ついには疲れ果てて立ち止まってしまいました。再び彼らが星の位置から方角を確認すると、出発地点よりも南へ遠く離れてしまっていることがわかりました。自分たちが北へ向かって歩いているよりも、もっと早いスピードで南に移動している氷山の上を彼らは歩いていたのです。自分は神の御心に従い、正しい方向に歩んでいると思っていても、実は神から遠く離れてしまっていないか、過信せず、吟味しましょう。
2,救いをないがしろにするな!
イエスの福音は御使いが伝達した律法にまさる
2章2節で語られているのは、御使いが律法の伝達者であったことです。旧約の中心である律法が、御使いを介して民に与えられたと言います。そういう理解をしていなかった方もあると思いますが、確かに聖書にはそういう記述が見られます。申命記33章2節「主はシナイから来て、セイルから彼らを照らし、…幾万もの聖なる者のところから近づいて来られる。その右手に御使いたちを伴って」と書かれ、ステパノの説教で「あなたがたは御使いたちを通して律法を受けたのに、それを守らなかったのです」(使徒7:53)とあります。
しかし、3節にあるように、福音、救いのことばは、「初めに主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとして私たちに示したもの」であり、4節では、「そのうえ神も」、不思議な御業や、聖霊の賜物によって、それを証言されていると語っています。不従順な者への警告と刑罰を含むモーセの律法と、主イエスについての教えとが対比されているのです。
福音の力を経験していますか
すると、この対比を律法を非寛容で厳格な戒めとみなし、新約の福音を癒し、慰めをもたらすものであると考えやすいのですが、ここで著者が言おうとしていることはそういうことではありません。福音は、確かに平安を与え、愛に満ち、優しさと心にぬくもりをもたらしてくれますが、同時に、私たちを力づけ、挑みかかるようなメッセージであり、生き方を根底から変えてしまうような力強いものです。福音は、心地よい毛布のようなものではないのです。4節で「しるしと不思議と様々な力あるわざ」という表現がありますが、福音によってもたらされる神の御業のことが示唆されています。さらに「聖霊」のことが触れられていますが、聖霊が福音を信じ従った人々の間で、その内側に宿られ、彼らに喜びと力を与え、その心を揺さぶり、新しい異なる生き方へとチャレンジし、個人を、そして共同体をエネルギーに満ちたものへと変革するものであることを明らかにしています。
2節に「救いをないがしろにするな」ということですが、このことばを自分自身に問いかけた時、自分は神を信じているし、イエスさまを主と仰いでいるし、信仰生活を送っているので、「私は救いを軽んじてなんかいない」と思ったのですが、しかしほんとうにそうだろうか、と心探られる思いがしました。それならば、自分の生活で、教会で、イエスの福音が真実であり、力強いという証拠が明らかにされているのか、と迫りを感じました。思いを新たにみことばに向かい、救いをないがしろにせず、押し流されることのないように注意して歩みましょう。