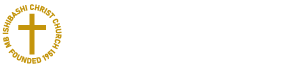ヘブル人への手紙 5:11ー6:12
礼拝メッセージ 2025.5.11 日曜礼拝 牧師:船橋 誠
1,霊的成熟を目指して進もう(5:11〜6:3)
霊的状態を心配する
13章23節に「私たちの兄弟テモテが釈放されたことを、お知らせします。もし彼が早く来れば、私は彼と一緒にあなたがたに会えるでしょう」と書いています。テモテとこの手紙の著者とは、宛先の人々にいつか会いに行く予定であったことがわかります。この手紙の著者は、宛先のユダヤ的背景を持っているキリスト者たちに会いたいと思っていたのです。それは、彼が牧師として彼らのことをとても心配していたからです。なんとかして、彼らがイエス・キリストを日々見上げて、神への信仰に堅く立つことができるようにと祈っていたのです。それというのも、今日の箇所から想像できるとおり、彼らの多くが霊的に後退し、信仰がダウンしていたからです。11節には「このメルキゼデクについて、私たちは話すことがたくさんありますが、説き明かすことは困難です」と言っています。実は7章から10章にかけて「メルキゼデク」のこと、すなわちイエス・キリストの大祭司というお働きのことについての説明が詳しく展開されるのですが、それに先立って、言っておきたいことがあると、著者は書いたのでした。
霊的に赤ちゃんのまま
それは一言で表現するなら、「あなたがたはまだ霊的には赤ちゃんのままではないですか」という強烈なことばのパンチです。11節から14節を見ると、「固い食物」と「乳(ミルク)」、「大人」と「幼子」という対比的表現でわかるように、成長すること、成熟していくことが必要であると強く命じています。おそらく彼らの中に霊的に未熟な人々が多くいたからでしょう。もちろん、信仰を持った最初は、だれでも霊的に未熟ですし、幼子のようであるでしょう。けれども彼らはそうではありませんでした。12節に「年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神が告げたことばの初歩を、もう一度だれかに教えてもらう必要があります。あなたがたは固い食物ではなく、乳が必要になっています」と言われなくてはならない状態でした。
霊的未熟の原因
彼らの信仰が停滞していた理由は何だったのでしょうか。11節後半では「あなたがたが、聞くことに対して鈍くなっているからです」と書いてありますが、この「鈍くなっている」(ギリシア語はノースロイで直訳すると「鈍い者たち」)ということばは「怠ける」という意味のことばでもあります。同じ単語が6章12節では「怠け者」と訳されています。ですから第一に、彼らの霊的な無知の原因は、怠惰から来ているのだということです。確かにみことばを継続的に学び続けることはいつの時代にも簡単なことではありませんが、私たちもみな学び続けていかなくてはならないのです。
さらにここで注目すべきことは、それが第二のことなのですが、彼らの問題は教理が単なる知的理解にとどまっていたということでしょう。実践的な信仰理解が必要であるのに、あなたがたはそれをまだ得ておらず、ミルクばかり飲んでいるのだと、5章14節に記されています。それが「善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された」という表現に現れています。基礎編をマスターしたならば、必ず次のステップ、応用編へと進まなくてはなりません。それは信仰が日常生活において生きたものになるということです。これをすることは良いことなのか、それとも悪いことなのか、が判断できなくていけないのです。もちろん、すべてのことについて白黒をはっきりできるわけではないのですが、これを行うことは、神に喜ばれることなのか、またイエス様だったどうするだろうか、といった問いをもって、みことばに聞いていくことが大切です。それはインターネットで検索して答えを探すような簡単なものではなく、日々聖書に親しむ中で霊的な目が徐々に養われていくという習慣が求められます。パウロによるローマ人への手紙にあるように、「神のみこころは何か、すなわち、何が良いことで、神に喜ばれ、完全であるのかを見分ける」(ローマ12:2)ということが必要なのです。
2,最後まで信仰の確信に立ち続けよ(6:4〜12)
難解な箇所
6章4節から8節まではどう理解すべきか、解釈上、難解な箇所として知られています。これらのことばから、ある人々は一度救われたとしても不従順を続けるならば救いを失い滅びてしまうことがあると言います。しかし、聖書の他の箇所には一度救われたならば、決して滅びないと約束されているので(たとえばヨハネ10:28〜29)、ここが記しているのはそういうことではなく、実際にそういうことがあるというのではなく、あくまで想定上の内容であると考える人もいます。あるいは、ここに記されているのは救われているように表面上見えたが実は救われておらず、神に敵対するようになった者たちを指すと考える人もいます。詳しく論じることはできませんが、それを解く鍵となることばを一つ挙げておきたいと思います。それは6章4節にある「不可能である」ということばです。これは邦語訳では6節で「〜ことはできません」と訳されていますが、ギリシア語のほうでは、4節の最初に「なぜなら不可能である」(アデュナトン・ガル)と書いて、そのあとの文章「一度光に照らされて…」が続いていきます。
警告と激励
ここで著者は、「こんなことはあり得ないはずだし、断じてそうなってはならない」として、読者に向かって厳かに警告しているように感じます。絶対あり得ないほどの最悪の事態を前もって語ることで、「あなたがたには前進あるのみです。決して後退してはいけません。それはたいへん危険です」と呼びかけているのです。だから、それが9節の文章へとつながります。「だが、愛する者たち。私たちはこのように言ってはいますが、あなたがたについては、もっと良いこと、救いにつながることを確信しています」と。続いて9節から12節を読むと、そこには信仰による愛のわざに、いわゆる奉仕に励むよう勧められています。これは、5章11節からのところで、霊的に成熟した大人になりなさい、という命令に呼応した構成になっています。5章11節に出てきた「鈍い」(ノースロイ)ということばが6章12節では「怠け者とならずに」と出てくると言いましたが、ここで言われていることは、つまりこういうことでしょう。「あなたがたのことを鈍い者、怠け者と私は言ったが、私の切なる願いはあなたがたが『怠け者とならず』あるいは『鈍い者とならず』(ギリシア語文では「メー・ノースロイ」で、メーは否定辞)、そういう歩みから脱却して成長し、最後まで信仰の確信をもって神からの変わらぬ約束を受け継ぐ一人ひとりであってください!」と。