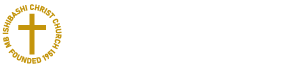ヘブル人への手紙 4:14ー5:10
礼拝メッセージ 2025.5.4 日曜礼拝 牧師:船橋 誠
1,天を通られた私たちの大祭司(4:14〜16)
大祭司について
旧約聖書の時代から行われてきた神殿でのいけにえ制度やさまざまな儀式のことなどをベースに、ヘブル書の著者は最も語りたいお方のことについて説明しています。そのお方とは、言うまでもなく、イエス・キリストのことです。イエスさまについていろいろな説明がこの書でなされますが、ここでは「大祭司」という働きを中心に述べています。大祭司の根本的な役割は、神さまと民との間に立って、彼らの代表として、いけにえを捧げ、その執り成しをすることにありました。
もろもろの天とは
14節「私たちには、もろもろの天を通られた、神の子イエスという偉大な大祭司がおられる」と記しています。この「もろもろの天」という表現は、「天」(ギリシア語:ウラノス)の複数形です。当時のユダヤ世界では、「天」というものは幾つもの層からできているものという理解がありました。もちろん、その一番高いところ、その中心に天の神さま、父なる神がおられます。イエスさまが十字架にかかられ、よみがえられた後、天に昇られましたが、それはただ、地上でのわざを終えて、霊的な領域に行って、安息の場所に移られたことを意味していません。イエスさまの昇天は、幾層もの天を通って行かれ、栄光の父なる神が座したもうところ、神の御座にまで至られたことをここに伝えているのです。地上で大祭司が垂れ幕の向こうにある至聖所に入ったように、イエスさまは直接、栄光の御座にあって、御父の前において私たちのために執り成しをしてくださっているということです。16節を見ると、私たちにはこの偉大な大祭司が与えられているので、このお方を通して、「恵みの御座」に近づくことができるし、大胆に近づくべきだとヘブル書は語り、勧めています。14節で「信仰の告白を堅く保とうではありませんか」というのは、当時も今も、日々さまざまな圧迫を感じて疲れを覚え、信仰による希望を抱くことにもあきらめを感じている人々に対する激励のことばです。「この偉大な大祭司イエスにあなたの信仰と希望のすべてを委ねなさい。勇気をもって大胆にイエスさまに信頼して歩みましょう」と、みことばが強く勧めています。
2,弱さに同情できる私たちの大祭司(5:1〜4)
大祭司の条件
5章1節から読んでいくと、具体的に大祭司という職務を行う人がどのような者でなければならないか、その資格や条件について説明されています。その重要な資格の大前提は、「大祭司は人間でなければならなかった」ということです。1節にあるように、「人々の中から選ばれ」た者であることが絶対に必要なことでした。人間であることの重要な点が2節で説明されています。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができます」と。「自分自身も弱さを身にまとっている」という点ですが、これは4章15節で「私たちの大祭司」である主イエスが、「すべての点において、私たちと同じように試みにあわれた」ということの中によく表されています。それは、たとえ罪を犯すことがなくても、誘惑にあうし、試練も受けるし、弱さや限界性を感じて生きている、ということです。
イエスさまに目を向けよう
私たちは、人生の中で起こり得るさまざまな苦労、痛み、悲しみということを知っています。しかし、それは実際に自分の身の上に起こって経験するまで、知識として理解しても、また多少想像はできても、ほんとうのところはわからないと思います。貧困生活、暴力やいじめによる苦しみや恐怖、孤独や喪失経験、さまざまな病気など、みなそうです。しかし、イエスさまに目を向けてください。このお方は、貧しさの中に育ち、喉の渇きを感じ、疲れを覚え、飢餓を経験されました。また、だれからも理解されず、孤独を味わい、病を知り、ひどい暴力を受けてボロボロになり、残忍な極刑をもって殺されてしまったのです。それゆえにイエスさまは「すべての点において、私たちと同じように試みにあわれた」ので、「私たちの弱さに同情できない方ではない」のです。
さらに注目すべき表現は、5章2節の「優しく接する」(ギリシア語:メトリオパセオー)という、あまり見かけないことばです。これは「感情を抑制する」という意味の語であり、「中間的な立場を取る」というニュアンスがあるそうです。つまり、こういうことです。過度に同情的でも、また逆に無感情でも、「無知で迷っている人」を助けることができません。過度に同情的で共感できても、自分自身がその問題の渦に巻き込まれ、悲しみや恐怖で動けなくなってしまうことがあります。他方、冷静で無感情である場合、他の人の気持ちや問題に気づかず、助ける行動を起こせないことがあるでしょう。メトリオパセオーというのは、その真中にあって、完全に共感しつつも、自身の視点と判断力を失わないので、正しく、しかも温かい愛の心をもって、「優しく接することができる」ということです。
3,苦しみ祈られた私たちの大祭司(5:5〜10)
7節でキリストは「大きな叫び声と涙をもって祈りと願いをささげ」たことが記されています。このところが示唆しているのはゲツセマネでの祈りの場面だと考えられています。キリストは血の汗を流し、死ぬほどの苦しみを味わわれました。イエスさまは苦しんで叫び声を上げられ、涙を流されたのです。8節には、そうした経験によって、「従順」を学ばれたと書かれています。信仰の視点に立てば、イエスさまは神であり、神的ご性質を持っておられたことにばかり目が行くかもしれませんが、同時に真の人間であられたということをここに見ることができます。人間である限り、弱さを身にまとい、試みを受けるし、苦しんで叫んだり、涙を流すこともあります。また、人間なので、身体的にも精神的にも成長します。だから、ここにキリストは「信仰の従順」、あるいは「神への絶対的信頼」を学んでいかれたのだと言われているのです。『ワード聖書注解』によれば、これらヘブル書の著者の視点は非常に実践的なもので、それは私たちに「真剣な祈りに励むこと」を教えているといいます。新約学者R.ブラウンは、この箇所の注解で、「祈らないことがすべての罪の根源である」と言い、あるいは「祈らないことは実践的な無神論である」とさえ言っています。毎日祈りの時間を割かないことは、神の手助けなしに人生を乗り切れると主張していることになるからです。それは、神を信じてはいるが、神がおられなくても人生は大丈夫だと告白するようなものです。神への祈りというこの霊的莫大な資源を忘れずに、日々真剣に祈りにともに励みましょう。