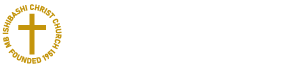ヘブル人への手紙 11:17ー31
礼拝メッセージ 2025.9.28 日曜礼拝 牧師:船橋 誠
1,著者が見つめる「信仰」とは
ヨセフの信仰のどこを見るか
ヘブル人への手紙11章が、「信仰の章」と呼ばれ、多くの旧約聖書人物の信仰の歩みが取り上げられ、語られています。ですから、「信仰の英雄たちの章」や、「旧約聖徒の殿堂」と呼ぶ人もいて、まさに信仰の一大パノラマを見る思いがします。
この箇所を読んで、たいへん興味深いのは、イサク、ヤコブ、ヨセフについて、どんなことを彼らの信仰による行為として著者が評価しているのかということです。たとえば、ヨセフについて見てください。「信仰によって、ヨセフは臨終のときに、イスラエルの子らの脱出について語り、自分の遺骸について指示を与えました。」(22節)と述べられています。この著者の着目しているところを不思議に思われませんか。なぜ、それなのですか?と聞いてみたくなる内容です。
ご存知のように、ヨセフと言えば、族長時代の人物で、父ヤコブの大家族の中で生まれました。彼は父によって特別扱いされたことから、ほかの兄弟たちから妬まれて、穴に投げ込まれ殺されかけました。しかし、結局エジプトへ奴隷として売られていって、その後もずっとそこで暮らすことになりました。彼は人生のどん底を味わった人です。しかも、奴隷となってからも、冤罪で監獄に入れられてしまいます。それでも、彼はあることをきっかけに大帝国エジプトのナンバー2の支配者の地位、宰相になったのです。
しかし、聖書には、「信仰によって、ヨセフは夢の解き明かしを通して、奴隷からエジプトの宰相になりました」と記されませんでした。波乱万丈の生涯を送ったヨセフのどこに著者は注目したかと言えば、「信仰によって、ヨセフは臨終のとき…」と、生涯最期の日に語った遺言に焦点が当てられています。
イサクとヤコブの信仰のどこを見るか
さらに言えば、イサクについても同じことが言えます。目も霞んで見えなくなった老年のときのことが取り上げられています。それはヤコブとエサウを祝福したことです(20節)。また、ヤコブはどうでしょうか。21節「信仰によって、ヤコブは死ぬときに…」とあります。石を枕にして野宿の旅を続けたこと、ラバンのもとに身を寄せてレアとラケルと結婚したこと、ヤボクの渡しで主の使いと格闘したこと、そして兄エサウと和解できたことなど、彼にもいろいろなドラマがありました。その全部が、ヤコブの信仰に大きく関わっています。しかし、著者はヤコブについても、その生涯の終わりのこと、彼が「死ぬときに、ヨセフの息子たちをそれぞれ祝福し」たことを記録しています。明らかにヘブル書の著者には明確な意図がありました。読者に伝えたいこと、それを知って欲しいから特別にその部分を切り抜いて、提示しているのです。
2,死を超える神の約束への信仰
族長たちの信仰について
では、ヘブル書の著者のここでの選択ポイントとは何だったのでしょうか。それは彼らの「死を超える神の約束への信仰(あるいは信頼)」です。著者はこれら族長たちの中に、死を超えて後も残り、やがて成就する神の約束に対する信仰を見ていました。アブラハムのところを見ると、17節です。「信仰によって、アブラハムは試みを受けたときにイサクを献げました。約束を受けていた彼が、自分のただひとりの子を献げようとしたのです」。これは、創世記22章に記されている出来事です。
アブラハムの一族に、不妊で高齢だった妻サラを通して、一人息子イサクがやっと授けられたのです。しかし、このせっかく与えられ、大きくなった大事な跡取りを「献げよ」というのはどう考えても大きな矛盾であり、不条理極まりないことです。しかし、頭では理解不可能な神からの命令にアブラハムどのように従うことができたのかが、ここに記されています。それは、神が結ばれた約束を、神はどんなことをしても必ず絶対に成就されるという信仰でした。それが「神には人を死者の中からよみがえらせることもできる」(19節)とアブラハムが受け止めたということでした。これが、「死を超える神の約束への信仰」です。
また、イサク、ヤコブ、ヨセフについても同じことが示されています。自分の死が迫ったとき、イサクは息子のヤコブとエサウを祝福しました(創世記27:27〜40)。ヤコブは、ヨセフの息子たちを祝福しました(創世記47:31)。また、ヨセフは自分の死後の遺骨について指示を与えました(創世記50:24〜25)。彼らに共通するのは、死が神の御心を阻むことは決して無いのだという確信を持っていたことでした。彼らは、自らの死を超えて、神がその子孫たちに約束された報いがあるとことを忘れなかったのです。
神の約束された確かな未来へ
しかし、私たちが知っているように、これら族長たちについて見ると、約束の完成を生きている間に見ることはなかったのです。それは、11章13節で記されている通りです。「これらの人たちはみな、信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していました」。
たとえば、アブラハムに対して、神は三つのことを約束されました。カナンの地の所有、彼の子孫による国民の発展、その子孫による世界の祝福です。しかし、アブラハムはこれらどれについても、その実現を見ることはありませんでした。族長たちは、神のことばに信頼し、その約束を子孫に伝え続けました。見たことのないものを信じ、見たことのないものをその子に託しました。継承できる遺産はなくても、神の約束こそが子孫に遺すべき大いなる宝であると考えたのです。たとえ、自分たちが死んでも、神の約束は決して死なないことを知っていたのです。信仰は真の意味で、神の約束された確かな未来へと私たちの心の目を向けさせるものです。
アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフなど、ここに出て来る人たちは、確かに信仰によって生きました。しかし、完璧な人間だったわけではないことは創世記を読めば、明らかです。信仰についても、人生についても、彼らはすべて模範的な歩みをしたわけではなく、浮き沈みの多い人たちだったと思います。超人でも英雄的な人物でもない、全く普通の人たちが、最後に信仰の人として、後の時代の人々への証しを残しました。「信仰は、望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるもの」(11:1)という信仰というものの不思議さを思います。自分の死を超えた先に、いつまでも残り、神の約束が果たされていくことへの確信、そういう信仰の世界が、「今」というときの私たちの見方を変え、生き方を変えてくれるのです。