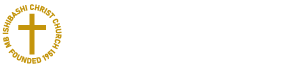ヘブル人への手紙 2:10ー18
礼拝メッセージ 2025.3.9 日曜礼拝 牧師:船橋 誠
1,来たるべき世の統治者イエス
「これから世界はいったいどうなっていくのだろうか」という不安と恐れは、現代の私たちと同じように、このヘブル人への手紙が書かれた時代にも、人々の間にあったと思います。新約学者たちの多くは、この書の執筆年代を紀元70年より少し前と考えています。70年にはローマ軍による攻撃でエルサレムは陥落し、神殿は跡形もなく破壊されてしまいます。しかし、この神の都の破滅へと向かうカウントダウンの中、キリスト者たちは希望の光を見出していました。それが「来たるべき新しい世界」がいつか到来するという預言でした。
5節の「私たちが語っている来たるべき世を」とは、そのことを指しています。まだ見ぬ新しい世界、神が完全にご支配される、正義と愛による美しい秩序が打ち立てられる日が、必ず来ると聖書は語っており、この手紙はその希望と確信を明確に伝えています。主イエスが二千年前に来臨された時から、それは始まりました。そして将来において完全に成就することになります。現在という時代は「すでに」と「未だ〜ない」の緊張関係の中にあります。そこでこの書が記すのは、誰が「来たるべき世」である「神の国」において、王として立てられ、治めることになるのか、それがここに説明されていることです。
「来たるべき世」を治めたもうお方は、どんなに優れて偉大なのか、どんなに強いパワーを持っているのかということを、普通に考えたら、そういうことが重要なことであると思うことでしょう。けれども、聖書は言うのです。「この王となられたイエスは、十字架にかかられ、呪われた者となって死んだお方です」と。それはまさに「ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなこと」(Ⅰコリント1:23)に見えます。死ぬということ、さらに「死ぬことの苦しみ」という、人間にとって一番マイナスに感じられることが、神が立てられたこの王の最も優れた、偉大な御業であると、この書は証ししています。ここに神のご計画の根本を理解する鍵があるのです。「死の苦しみをすべての人のために味わわれたイエス」について、10節以降で詳しく述べられています。
2,救いの創始者イエス
第一に、すべての人のために死の苦しみを受けたイエスは、「救いの創始者」と呼ばれています。この「創始者」という表現は、12章2節にも出てきます。そこでは「信仰の創始者」とあります。このギリシア語は、それを最初に始めるという「創始者」という意味と、それから人々をリードして導いていくという「指導者」の意味があります。おそらくそのどちらのことも含んだ意味で、著者は使っているのでしょう。英語では、古くは欽定訳では「キャプテン」(船長)と訳されていました。また、最近の多くの英語訳では、「パイオニア」(開拓者)と訳されています。
10節を読むと、「多くの子たちを栄光に導くために、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全な者とされたのは、万物の存在の目的であり、また原因でもある神に、ふさわしいことであった」と記されています。救いと栄光に私たちを導くために、イエスは先頭に立って、開拓者として、突き進んでくださったというのです。イエスは探検家のように、ジャングルの奥深くへと進んで行き、誰も通ったことのない、道のないところを切り開いてくださいました。そのジャングルには、危険が多くあり、苦しみ、痛み、罪、死に満ちた世界だったのです。しかし、そこに救いの道を開通してくださいました。それがイエスというお方です。
3,奴隷状態からの解放者イエス
第二に、すべての人のために死の苦しみを受けたイエスは、「恐怖からの解放者」でした。14節と15節を見ましょう。「そういうわけで、子たちがみな血と肉を持っているので、イエスもまた同じように、それらのものをお持ちになりました。それは、死の力を持つ者、すなわち、悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖に一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした」。
御子イエスが「血と肉」を持つとは、死すべき存在になられたということです。単純に考えると、死ぬことはない不老長寿で、不死身の強健な肉体を持つ者になることもできたはずです。しかしそうされずに、むしろイエスは死ぬ者となり、そしてご自分の「死」によって、「死」という敵と、「悪魔」を滅ぼしたのです。14節で「滅ぼす」と訳されていることばは、「無力化する」、「無効にする」という意味のことばが使われています。主イエスの十字架によって、死と悪魔の力はすでに無力化されています。今や悪魔は、凶暴な番犬のように太い鎖に繋がれており、たとえ吠えても、私たち危害を加えることができないのです。
4,あわれみ深い大祭司イエス
第三に、すべての人のために死の苦しみを受けたイエスは、「あわれみ深い大祭司」として、私たちのためにとりなしをしてくださいます。18節をご覧ください。何度も読んで心に刻んでください。「イエスは、自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです」。神殿で仕える祭司は、神の民の代表として、神のあわれみ深さと忠実さを体現する必要がありました(17節)。そして同時に必要なことは、神の民として生きている人々と共感できる存在でなくてはなりません。
「イエスは、自ら試みを受けて苦しまれた」というのは、単に一人の人間として生身のからだを持ち、痛かったり、苦しがったり、悲しい経験を通ったということではありません。9節を思い出してください。「その死は、神の恵みによって、すべての人のために味わわれたものです」。「すべての人のため」の生涯です。そして「すべての人のために死を味わわれた」ということです。では、「すべての人のために味わう死」とは、何でしょう。当然、一人の人間として味わう死とは全く次元が異なっているものです。
ある神学者がこんなことを書いています。人が人生でどんなに絶望的な場所に立っているとしても、イエスさまの十字架はそれよりももっと低く、もっと暗いところに立っている、と。人が味わう苦しみのすべてを、罪の悲惨を、どん底にくだって味わい尽くしてくださったのが、イエスの十字架です。使徒信条の中に「主は…陰府にくだられた」とありますが、それはキリストが味わわれた苦しみの大きさだと理解できるでしょう。恐るべき孤独と、暴力と、残虐非道が支配するようなおぞましい地獄のような世界、そこにイエスはくだってくださったということです。ですから、こう宣言できます。「今日、明日、明後日、私たちが直面するどんな問題でも、イエスが共感し、助け、救うことができないものは何もないのだ。」(N.T.ライト著『NT for Everyone Hebrews』)。