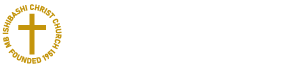ヘブル人への手紙 3:7ー19
礼拝メッセージ 2025.4.6 日曜礼拝 牧師:船橋 誠
1,聖霊からの警告
「今日、もし御声を聞くなら、あなたがたの心を頑なにしてはならない」と、警告のことばが発せられています。このような警告する文章が五箇所あり(2:1〜4、3:7〜18、6:4〜8、10:26〜31、12:25〜29)、今回の箇所はその二番目の警告です。警告というのは、私たちの耳に心地よいものではありませんが、いろいろな危険から身を守るためのものですから、緊急かつ最重要の事柄です。親や教師が子どもたちの安全のために注意を与えるのと同じように、神はご自分の子とされた私たち一人ひとりに対して、心を配っておられ、愛をもって注意を喚起しているのです。ある説教者は、この箇所を自動車の運転で居眠りをしてしまうことの危険にたとえ、また別の説教者は火災のビル10階に取り残された人の例を挙げていました。私はこの聖書箇所に繰り返し目を通しながら、「私って大丈夫なの?」と自問する思いでした。ちょうど、最後の晩餐の席上で、主イエスが「あなたがたのうち一人がわたしを裏切ります」と語られて、弟子たちが不安になって「まさか私のことではないでしょう」と次々に主に尋ねた場面のようにです(マタイ26:17〜19)。
2,荒野の四十年間
7節から11節をよく見ると、カギ括弧で括られており、旧約聖書からの引用文であることがわかります。それは詩篇95篇7節から11節です。出エジプト記や民数記に描かれた神の民が荒野を旅していく中で起こった出来事について語られているのです。エジプトで奴隷として苦役を強いられていたヤコブの子孫たちが神の大いなる御手に導かれ、モーセを先頭にエジプトを脱出しました。しかし、民が約束の地に至るまで、荒涼とした砂漠で四十年間さまようことになりました。神は、道なき道を行く彼らを昼は雲の柱、夜は火の柱で導き、マナやうずらを与え、岩から水を出して養いつつ、ひたすら宿営と移動の連続である集団的放浪生活を助けられました。
しかし、このいわゆる「荒野の四十年間」において、民の側はどうであったかと言えば、残念ながら彼らは絶えず不平を言い、神に背いて指導者モーセを苦しめました。とても苦しい「四十年間」でしたが、9節にあるように彼らは荒野で日々神の御業を見たはずです。けれども、民の大部分は、心頑なにし、神を試みて、逆らい、罪を犯し続けました。私はこの「荒野の四十年間」が、どの時代の誰にとっても象徴的なものであると感じています。ヘブル人への手紙の著者が紀元60年代のユダヤ的背景を持つキリスト者たち、そして諸教会にこのことばを差し向けたように、現代の私たちにもこれらのメッセージは「聖霊の御声」(7節)として「今」語られているのです。
3,生ける神から離れるな
主は私たちの中におられるのか
具体的な勧めとして、語られている12節から14節を見たいと思います。第一番目が12節です。「兄弟たち。あなたがたのうちに、不信仰な悪い心になって、生ける神から離れる者がないように気をつけなさい」。「気をつけさない」との忠告は、それ以降の命令も同じですが、「自分自身の信仰は大丈夫なのか」ということとともに、「あなたがたのうちに、…生ける神から離れる者がないように」と、自分の周りにいる人たちに目を向けるように注意がされています。「生ける神」という表現は、この手紙の著者がよく使っていることばです(9:14、10:31、12:22)。神は確かに存在しておられ、生きて働いておられるし、私たち信仰者たちの群れを、そして各々の人生の旅路を導いておられる神であるということです。それが見えなくなっていませんか、あるいは見えなくなっている人がいませんか、ということです。メリバの水の場面、出エジプト記17章17節で民はこう言いました。「主は私たちの中におられるのか、おられないのか」と。聖書は語ります。彼らが荒野で試みられたというより、荒野の中で彼らのほうが、「神はいるのか、いないのか」と言って神を試みたのであるというのです。それは、神の存在を信じるか否かということに留まらず、自分の歩みの中に神は確かに生きておられると確信できていますか、という問いかけです。「神は私たちの中に生きておられる『生ける神』です」と告白しつつ生きていくことが求められていることです。
互いに励まし合いなさい
13節「『今日』と言われている間、日々互いに励まし合って、だれも罪に惑わされて頑なにならないようにしなさい」。「生ける神から離れる者がないように」するために、私たちが取り組むべきことは、「日々互いに励まし合う」ことです。この「励ます」(ギリシア語パラカレオー)の語源的意味は「助けを与えるためにそばに立つ」ということです。それで著者が聖霊によって命じていることは、「互いにそばに立って助け合いなさい」ということになります。
さらに、「今日」という大切なキーワードを見ておきたいと思います。「今日」ということばは、4章に入ると、「安息」に入るという未来的視点も示唆されますが、今日のところでは「ただちにそうせよ」という緊急性のニュアンスと、一度きりしかないかもしれない「一回性」という意味の「今」を表しています。コリント人への手紙第二6章2節を思い起こさせます。「神は言われます。『恵みの時に、わたしはあなたに答え、救いの日に、あなたを助ける。』見よ、今は恵みの時、今は救いの日です」。「今日」すべきことを先延ばしにしたり、神への応答を後回しにしてはならないのです。
信仰は継続
14節「私たちはキリストにあずかる者となっているのです。もし最初の確信を終わりまでしっかりと保ちさえすれば、です」。この「あずかる者」(ギリシア語メトコス)ということばも、特徴的表現です(1:9、3:1、6:4、12:8)。これは「仲間」、「パートナー」、「共有する者」を意味します。私たちはともに、「天の召し」にあずかり、「キリスト」にあずかり、「聖霊」にあずかり、「人生の訓練」にあずかってる人々の集まりです。私たちは天的で特別な仲間、共有者たちなのです。その感覚はどこから生じていくかと言えば、それが「最初の確信を終わりまでしっかりと保つ」ことです。ここで著者は、信仰は継続性のあるものとして教えています。ずっと信頼して生ける神から離れず、互いに励まし合い、キリストにあずかる者同士、旅の終わりまでしっかりと手を取り合って進んで行きましょう。