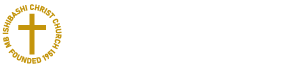ヘブル人への手紙 3:1ー6
礼拝メッセージ 2025.3.16 日曜礼拝 牧師:船橋 誠
1,イエスのことを考えなさい
1節の終わりで「イエスのことを考えなさい」と著者は命じています。元のギリシア語は異なりますが、12章3節でも「反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい」と記しています。私にとって、この聖書箇所での神さまからの最初の一撃は、この「イエスのことを考えなさい」でした。私はいったいどれだけ、イエスさまのことを考えて、日々生きているだろうか、と問われている気がしました。ヘブル人への手紙を受け取った当時のユダヤ人クリスチャンたち、諸教会の人たちも、必ずしもイエスさまのことを常に考えて、上よりの力を得て、喜びに溢れて生きていたのではなかったから、このような命令を著者は繰り返し記したのだと思います。人生が荒波に飲まれるような困難に直面し、失望と落胆が日常となり、罪と悪魔の誘惑に抵抗することが不可能に感じられるとき、私たちはイエスから目を離さず、イエスのことを考えて歩むように、教えられる必要があります。パウロも弟子テモテに言いました。「イエス・キリストのことを心に留めていなさい」(Ⅱテモテ2:8)。
繰り返しになりますが、この書の最後のほうで、「イエスから目を離すな」(12:2)とありますが、そういうことだと思います。喜びも力も湧いてこないのは、イエスから目を離していて、イエスのことを考えていないからです。マタイの福音書14章にあるペテロが水の上を歩く話を思い出します。「来なさい」と仰るイエスのところへ行こうとペテロは水の上を歩き出したのです。ところが沈みかけました。どうしてでしょうか。ペテロはイエスさまを見ずに、「強風」を見たのです。そして怖くなって沈みました(マタイ14:22〜33)。イエスから目を離して、自分を見たり、周りを見て、恐れと不安に取り憑かれ、気づくと主の喜びがかき消されているのです。イエスに意識を集中しましょう(ピリピ3:7〜10)。
2,イエスがどんな方なのか知る
使徒であるイエス
イエスのことを考え、集中するために、どんなお方であるのかを知らなくてはなりません。それでイエスさまのことを、著者は「使徒」そして「大祭司」と呼んでいます。「大祭司」は後述するので、ここでは「使徒」というほうに焦点を当てましょう。イエスさまが「使徒」であるという理解は、あまり馴染みがないように思います。多くの場合、「使徒」と言えば、イエスに召された十二人の弟子たちのペテロやヨハネのことや、あるいはパウロのことを思い浮かべると思います。 「使徒」はギリシア語でアポストロスですが、それは「遣わされた者」という意味で、いわゆる国や王より遣わされた「大使」に与えられる称号でもありました。使徒や大使の仕事は、その人を遣わした国家や支配者である方を代表して、その権力と権威とをもって、支配者の願うところの務めを果たすのです。イエスは言われました。「わたしは自分から話したのではなく、わたしを遣わされた父ご自身が、言うべきこと、話すべきことを、わたしにお命じになったのだからです。」(ヨハネ12:49)。まさに、イエスは父なる神から遣わされた使徒でした。御父である神の権威と力を帯びて世に来られ、恵み、慈しみ、正義そのすべてを人々に示し、父の御心である十字架にかかられ、贖いの死を遂げてくださったのです。
モーセに勝る御子イエス
次に、2節以降でイエスさまのことを深く考え、黙想していくために、著者はモーセとの比較で説明していきます。モーセは、エジプトで奴隷状態にあった神の民イスラエルを脱出させて、約束の地カナンに向けて、荒野の旅を導いた人であり、イスラエルを代表する人物です。彼はシナイ山で、十戒を受け、民にそれを与えて、教え導きました。そのうえ、神の律法である五書を書いた人として尊敬され、彼の名は律法と同義語のようにユダヤ人たちに扱われてきました。また、彼は神の栄光のご臨在に直接触れた人物としても知られています。このようにモーセは人間としては、確かにたいへん偉大で、神に忠実で謙遜な人であり、ユダヤ人ばかりではなく、私たちクリスチャンや教会にとっても、非常に素晴らしい注目すべき存在であることに間違いはありません。けれども、御子イエスさまと比較するなら、モーセはたいへん小さな神のしもべにすぎなかったのです。その役割、立場、ご人格において、イエスはモーセに勝っていることが説明されています。
モーセは優れて忠実な人でしたが、彼は神のしもべであり、イエスさまは神の御子であるということです。しもべは相続者である主人の息子に勝ることはありません。イエスさまは「家」の主人であり、「家」を造った所有者ですが、モーセは「家」の一部であり、そこに属するしもべです。これらモーセとの比較によって、イエスの絶対性、永遠性、完全性がより明らかにされています。イエスご自身がこう明言されています。「もしも、あなたがたがモーセを信じているのなら、わたしを信じたはずです。モーセが書いたのはわたしのことなのですから。」(ヨハネ5:46)。そうです。モーセを信じることは、キリストを信じることです。
3,確信に立ち続ける
イエスのことを考えて日々歩むと何が大切になるか、それがここに記されている「家」です。私たちの生活空間の家や、家族のことではなく、「神の家」のことです。6節で、ある種の信仰告白と言って良い表現が出てきます。それは「私たちが神の家です」という一文です。この1節から6節までで、「家」(ギリシア語オイコス)ということばが繰り返し出て来ました。旧約聖書で「神の家」と言えば、神殿のことを指すことがありますが、ここはそうではなく、神の民である人々、主を信じる信仰者たちのことを指しています。6節の最初には、「キリストは、御子として神の家を治めることに忠実でした」と書いています。イエスさまがイスラエルという神の家を造られ、教会を造られました。そして、私たちもキリストのもとへ人々を導き、新しい信仰者たちを迎えていくとき、この「家」を建てる働きに加わっています。神こそが家の建設者であり、私たちはその建物です。モーセもそうでした。教会という神の家は、ここまでのところから明らかなように、ある番地に立っている会堂という建物のことではありません。神の民の集まりです。それを忠実に治め、導いてくれるお方がイエスさまです。このことを心に留めるなら、私たちは喜んで、このヘブル書の著者の如く、宣言できます。「私たちが神の家です」と。私たちが「神の家」と言い得るために忘れてはならないことは、6節に言われているように、確信と希望を持ち続けるということです。この「持ち続ける」ということが大事で、継続こそ現実の証しとなります。ヘブル書の宛先のユダヤ人クリスチャンたちは、押し流されそうになり、離れていこうとしていました。しかし、留まり続けることが、主に求められていることでした。確信を持ち続け、主に、神の家に留まり続けましょう(ヨハネ8:31)。