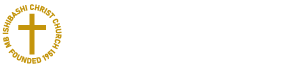ヘブル人への手紙 10:1ー18
礼拝メッセージ 2025.7.27 日曜礼拝 牧師:船橋 誠
1,律法という「影」に別れを告げよ(1〜4節)
この手紙の宛先の人々は、明らかに正しい信仰生活から遠ざかっていくような誘惑を受けていたと思います。しかし、それは、信仰が無意味だと思っていたとか、そもそも神さまが信じられなくなったのでもなかったのです。ただ、信仰の確信がなく、信仰による力が失われていたのだろうと思います。
それで彼らの中に起こっていた大きな誘惑は、ユダヤ教に逆戻りするようなことだったのかもしれません。でも、幕屋礼拝も、律法によるさまざまな祭儀も、それは実物、本物ではないと著者は明確に語ります。それは「影」にすぎないと。1節に「律法には来たるべき良きものの影はあっても、その実物はありません」と書いています。
1節から4節に、「完全にすることができない」、2節に「罪を意識する」、3節では「罪が年ごとに思い出される」とあって、これらの記述から、これまで旧約律法の枠組みで礼拝を捧げていた人たちの苦悩が見えてくるような気がします。もちろん、旧約聖書の聖徒たちも、律法に従って喜んで神に仕えていたことでしょう。けれども、すでにイエス・キリストの到来されたこの書が書かれた時点において、それを未だに続けている人たちの礼拝の姿を想像すると、喜びも確信もない様子だったことが伝わります。なんとも言えないような不全感、罪が思い出され、罪あることのみを意識し、信仰の力が湧いて来ない状態です。
2,キリストのことばで心を燃やせ(5〜10、15〜18節)
聖書を開いて
このヘブル書の箇所を黙想していると、イエス様の復活の記事の中にあるエマオの途上の話に出てくるクレオパともうひとりの弟子の姿と重なるような気がしました。イエス様が復活されたその日、エルサレムから約11キロメートル離れたエマオに向かってその二人の弟子たちは道々話しながら歩いているのです。そこへ、復活されたイエス様が彼らの前に現れてともに歩まれるのですが、彼らはそれがイエス様であることに気づきません。そして暗い顔をして、自分たちが望みをかけていたお方、イスラエルを贖ってくださるはずの方が、十字架で死んでしまったと落胆の色を隠せないのです。彼らを見ていると、「なぜ、気落ちしているのですか。眼の前にイエス様がいるじゃないですか」と教えてあげたくなります。しかし、そういう彼らがイエス様のご復活、生きておられることに気づくために、イエス様ご自身がされたことは、彼らがよく知っている聖書のことばを開いて、そして彼らの心を開いて、ご自分について書いてあることを説き明かすことでした。彼らは振り返って言います。「私たちの心は内で燃えていた」と(ルカ24:32)。
キリストのことば、聖霊のことば
実はヘブル書の著者も、ここで同じことをしています。著者は、ここで聖書を開いて説明します。しかも、ふたりのお方の直接の証言を紹介しています。そのふたりとは、キリストご自身と、聖霊様のことです。著者は、「キリストの御声を聞いてください、聖霊の語りかけを受け取ってください」と訴えています。これらの御声に耳を傾け、あなたがたの信仰を立て直し、キリストの御業に目を向けてください、と言います。
さて、5節から7節にあるキリストのことばとして述べられているところですが、当然ですが、福音書の記事を探しても同じことばは見つかりません。これは旧約聖書の詩篇40篇からの引用だからです。しかし、著者はキリストのことばとしてここに記しました。5節「ですからキリストは、この世界に来てこう言われました。」と。彼は受肉に先立つキリストのことばとしてこれを受け取り、ここに伝えています。大胆かつ貴重なことです。7節「今、わたしはここに来ております。巻物の書にわたしのことが書いてあります。神よ、あなたのみこころを行うために」。これは、イエス様のお気持ちをはっきり伝えることばで、主が父なる神のみこころを行うために、完全ないけにえとなってくださるために来てくださったことがよくわかる内容です。広い大地の真ん中に、イエス様がひとり立って、大空を見上げて、高らかに叫びます。「さあ、ここにわたしは来ました!あなたのみこころを行うために」と、そんな光景が心に思い浮かびます。
次に聖霊のことばが記されています。15節「聖霊もまた、私たちに証ししておられます」。このあとに書かれている文章も、旧約聖書からのものであり、エレミヤ書31章の引用です。これは8章で少し長く引用されていたことばです。一部を読みますと、聖霊はこう言われています。「わたしは、わたしの律法を彼らの心に置き、彼らの思いにこれを書き記す。」、「わたしは、もはや彼らの罪と不法を思い起こさない」。これら二つのイエス様と聖霊のことばを見ると、旧約聖書の時代から、神は予め当時の律法儀式を乗り越えるその先のことを示しておられたということです。いつか本物が、実物が現れるときが来ることがはっきりと予告されていたのです。
3,繰り返されることのないただ一度の御業(11〜14節)
ヘブル書が語っている旧約律法の礼拝と、キリストが成し遂げられた御業の新しい契約との対比にも注目しましょう。そこには確かに大きな違いがあったことがわかります。たとえば、「多くの祭司たち」と「キリストという唯一の大祭司」、「繰り返しささげられたいけにえ」と「キリストご自身という一度きりの犠牲」、完了していないゆえに「毎日立って礼拝の務めをする祭司」と、完了したゆえに「神の右の座に着座されているキリスト」等です。この中で特に「繰り返される」ということについて考えると、旧約律法の幕屋礼拝の不完全さがよく見えます。1節に「年ごとに絶えず献げられる同じいけにえ」とあり、11節に「同じいけにえを献げても、それらは決して罪を除き去ることができません」と記されています。
このようにキリストの完成した御業にあって、私たちは真の救いと恵みを受けているのです。ところが、不完全で繰り返し続けなければならない古いほうに、読者たちが引っ張られていたのは、いったいなぜなのか、と疑問に思います。これはあくまで私の推測ですが、人は神が完成された御業に全面的に頼って生きるよりも、無意味だとわかっていても、自分の力を使って、努力して決められた儀式を行い続けて、自分の手で救いを達成したい、罪を解決したいと願ってしまうものではないか、ということです。しかし、これは決して完成に至ることができず、いつか失敗に終わり、疲れと空しさだけが残ります。しかし、イエス様に心を集中して生きることは、その御業をただ受け入れるだけの受け身で消極的な生き方などではなく、信仰の行動を促すものです。希望を告白し、愛と善行に励み、礼拝や交わりに集まり続けていくのです。それは、「互いに〜し合う」という生き方です。