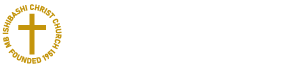ヨハネの福音書 7:37-52
礼拝メッセージ 2025.6.15 日曜礼拝 牧師:南野 浩則
生きた水
イエスは再び「水」の比喩で自己紹介をします。これはヨハネ福音書4章のサマリヤの女性との対話を思い出させます。ここでは水が霊であるという解説がつけられていますが、その霊はイエスの栄光と結び付けられています。イエスの栄光とは十字架の死であり、その後の復活です。人々がイエスの働きを真に理解し、それを担うことになるのは、イエスの十字架刑と復活を待たなければなりませんでした。
イエスの生まれ
イエスは神から選ばれ、遣わされた者なのか?この議論は、イエスの生まれた場所の論争へと繋がります。
【コラム】ベツレヘムについて
イエスが生まれたのはベツレヘムというユダヤの町であるとマタイ福音書、ルカ福音書は語ります。しかし、ヨハネ福音書は、イエスをガリラヤ出身と語るのみです。この理由は明確ではありませんが、ヨハネ福音書がこのように語っていると理解しておかないと、ヨハネ福音書をうまく読めなくなります。
メシアあるいは預言者はベツレヘムで生まれると人々は信じていたようです。少なくとも、ガリラヤ生まれの者ではないと確信していました。従って、この理屈からしますと、ガリラヤ出身のイエスはメシアでも預言者でもないことになります。その一方で、イエスの言動そのものに注目した人々は、そこに神のことばと業を見ました。出身地にこだわる伝承ではなく、イエスの言動そのものに意味を見出したのです。両者の視点の違いは、イエスに対する決定的な評価の違いとして表れました。
神の意思が優先されます
イエスに反対する人々は、やはりここでも当時の伝統や常識を根拠にしています。出自という伝統にこだわることで、イエスの言動が神に由来すること、それをイエス自身が証言していること、それらを認めたくないのです。伝統や習慣から世界を見て評価すること自体は問題ではないでしょう。そのような姿勢は誰もが持っているし、この社会が秩序立てられているのも皆が大切にしようとしている事柄を尊重しているおかげです。当時の人々からすれば、出自が明確でない者が自らを神が選んだ者として発言することは、社会や政治の混乱を呼ぶことになります。指導者たちの根底にはそのような理屈があったかも知れません。しかしそこにだけこだわっていては、神の意思が現われた時にそれを無視してしまうことになります。神の意思とは、人々が神のことばを大切に受け止め、虐げられている人々が救われ、貧しく追いやられた人々が十分に生活をできるようになり、人々が互いに尊重し合って生きることです。神の意思は伝統や習慣に優るのです。イエスの出自に文句をつけることは、その出自自体を問題にしたものか、それは単なる口実であったのか、よく分かりません。しかし、イエスの言動が神に由来するかどうか、それを見極めようとする基準を間違えていることは確かです。現代のキリスト者にも気を付けなければなりません。例えば、イエスはダビデの子孫として描かれ、それゆえにイエスがメシアであることの根拠付けは他の聖書箇所に記されています。それはそれで正しいのですが、そのような保証を聖書から受けたイエスだから信頼に足りうるということではないのです。イエスの言葉と業が神の意思を表している、そこを私たちのイエスに対する信頼の根拠としたいのです。その思いは、イエスを救い主とすることに私たちがとどまり自己満足に浸ることを防ぎます。むしろ、神の意思を私たちも表したいと願うことにつながるのです。