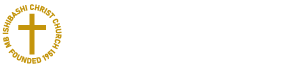コロサイ人への手紙 3:12ー17
礼拝メッセージ 2025.9.21 日曜礼拝 牧師:太田真実子
コロサイ人への手紙は、紀元60年代前半ごろに、小アジア(現トルコ)の町コロサイの教会の兄姉たちに向けて、パウロが獄中で書いた手紙だと言われています。コロサイ教会には、「異なる教え」「混合的な信仰」の影響を受けていたようです。それに対してパウロは、「キリストこそすべて」であることを主張し、キリストの救いの十分さと、新しい人として生きる生活の実践について教えています。
今回の聖書箇所の直前(3章前半)では、古い人を脱ぎ捨て、新しい人を着ること(=キリストにあって変えられること)が語られました。今回はその続きで、「新しい人=キリストにある者」が実際にどんな姿で共同体(教会)に現れるかということが示されています。それは、「同じキリストにあって生きる者としての行動規範」でもあります。
1,キリストにある者としての生活態度(3:12-)
12節冒頭「ですから」は、前節の「新しい人を着る」ことへの具体的な内容の導入です。神に「選ばれた」「聖なる」「愛されている」は、神との関係性を示し、そこにアイデンティティがあるということです。だからこそ、「深い慈愛の心」(憐れみ・同情)、「親切」(思いやり・やさしさ)、「謙遜」(へりくだり)、「柔和」(穏やかさ)、「寛容」(長く耐える力)を“着なさい”と命じられています。これらは単なる“良い性格”ではなく、神に選ばれ・聖なる者とされ・愛されている者としての身分やアイデンティティが生み出す具体的な態度です。衣服の比喩(着る)で、自分の意思によって日常的に身につけることが教えられています。
またさらに、13節では「互いに忍耐し合い」(相手の欠点をそのまま受け止める寛容さ)、「主が赦したとおりに赦す」(赦しの模範はキリストの癒し・キリストに根差した共同体の原理)ことが教えられています。共同体の和解は法的処罰ではなく、互いに赦し合うことによって成り立つ、ということです。
そして14節で「これらすべての上に、愛を着けなさい。愛は結びの帯として完全です」と命じられます。前述の心構えの上にさらに最も重要なものー「愛」を身につけることが強調されています。ギリシャ語の「愛」は、無償・犠牲的な愛を意味します。キリスト者としての具体的な態度の中核には愛があるべきです。
2, 召されて一つのからだとなった共同体として(3:15-17)
15節で、主体的に「キリストの平和」に自分の心の最終判断を委ねることが命じられています。「キリストの平和」は単なる個人的な安らぎのことだけではありません。キリスト成し遂げてくださった和解や回復の関係が含まれます。そして、キリスト者はこの平和のために神に召されて、一つのからだ(教会)とされました。また、「感謝の心」を持つ人になることも命じられています。平和と一致の土台には、感謝の心が大切です。現代の私たちも、争いや分裂があるとき、「キリストの平和」を基準にしていきましょう。自分の感情や正当性だけで裁くのではなく、和解と共同体の一致を目指す姿勢を大切にしたいと思います。
「キリストのことば」(16節)とは、現代の私たちにとっては聖書のことばです。聖書をとおして語られるキリストのことばが、共同体の日常生活に深く染み渡るようにしなさいと命じられています。また、前述で互いに寛容であるべきことが教えられてきましたが、ここでは「知恵を尽くして互いに教え、忠告し合う」ことも重要だと分かります。罪や弱さが放置され続けるなら、そこには平和や成長が生み出されていきません。
それから、「詩」(詩篇)、「賛美」(教会的伝統の歌)、「霊の歌」(聖霊に導かれる新しい賛歌・個人的/共同体的な賛歌)で、多様な礼拝音楽によって心から神に賛美することが教えられています。
そして最後の最も重要なポイントは、「ことばであれ行いであれ、何かをするときには、主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい」(17節)という視点です。「イエスの名において」とは、「イエスの権威のもとで行う」「イエスの性質・意図に一致して行う」「イエスを媒介として神に向けている」という意味を持ちます。
キリスト者の行いの基準はすべて、いつも主イエスの主権と神への感謝にあります。私たちの仕事、学び、人間関係、礼拝は、どれも「キリストの名において」行われているでしょうか。その根底には感謝の心があるでしょうか。
争いや分裂を経験するときには、自分の正しさではなく、「キリスト」を基準に考えましょう。私たちの心を、不安や怒りではなく、キリストの平和によって支配していただきましょう。キリストの平和が私たちの心を支配するとき、共同体には一致がもたらされます。