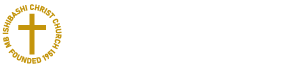ヘブル人への手紙 10:19ー25
礼拝メッセージ 2025.8.3 日曜礼拝 牧師:船橋 誠
1,こういうわけで、兄弟たち
今回の箇所は、この書のクライマックスの一つです。これまでのことを総合して、神が私たち人間に与えてくださった大きな救いとあわれみに私たちはいかに応答していくのか、導かれるのかを明らかにしています。19節「こういうわけで、兄弟たち。私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます」と始まっていきます。ちょうどパウロがローマ人への手紙で「こういうわけですから、兄弟たち。私は、神のあわれみのゆえに、あなたがたにお願いします。」(ローマ12:1第三版)と、それまでの内容を受けて、いかに生きるのかを促したのと同じです。ローマ書の場合は、「あなたがたのからだを神にささげなさい」という献身でした。ヘブル書の著者は、いくつかの「〜しようではないか」と勧告します。「神に近づこう」(22節)、「希望を告白し続けよう」(23節)、「互いに注意を払おう」(24節)などです。
ギリシア語文では、19節から22節が一つの文で、23節から25節がもう一つの文となっています。語彙数も多く、巧みにギリシア語を操る著者ですから、ここもかなり複雑な文章構造です。しかし、それを詳細に読み解くと、どこに強調点があるのかが見えてきます。私の理解では、この箇所の中心は、22節の「神に近づこうではありませんか」です。ですから、ここを短く要約するなら、「こういうわけで、兄弟たち。…全き信仰をもって…神に近づこうではありませんか」となります。
2,神に近づくことのできる理由とは
まことの聖所へ入る確信を持っているから
間に挟まれた文章が、なぜ神に近づけるのかについての説明となっています。著者は、その理由あるいは方法を二つ挙げています。一つ目がこれまで説明されてきたイエスの十字架の御業によって私たちはまことの聖所へ入れるという確信を持っているからということです。二つ目は、偉大な永遠の大祭司を私たち持っているということです。確信とは、ギリシア語文の直訳では「確信を持っている」です。
つまり、しっかりと信じること、信頼することです。このあとも、この書は信仰の驚くべき力を明らかにしていきますが、神に近づくために必要なことはまさに信仰です。ニューヘブリディーズ諸島で聖書翻訳宣教師として奉仕していたジョン・パットンは、その言語に「信仰」ということばが存在しなかったため、仕事が進まず困っていました。ある日、彼の下で働いていた現地の男が家に入って来て、大きな椅子にどかりと座り込みました。パットンは彼が行なった動作を表すことばは何か尋ねました。その男が答えたことばをパットンは新約聖書の翻訳で信仰と訳すことにしました。なぜなら、その男はその椅子が休息を提供することを確信し、何のためらいもなく、完全に自分の身を椅子に委ねたのです。私たちが神に近づくために信仰を持つ、確信を抱くというのは、そういうことでしょう。自分の心とからだを、自分の人生を、主イエス・キリストに委ねるのです。
偉大な祭司を持っているから
神に私たちが近づくことのできる根拠の二つ目は、21節にあるように「私たちには、神の家を治める、この偉大な祭司がおられる」ことです。この方は「ご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのために、この新しい生ける道を開いて」(20節)くださいました。旧約律法において定められていた幕屋礼拝の規定を、著者は繰り返し語ってきましたが、幕屋もいけにえも祭司も、すべて本物の模型にすぎなかったのです。本体、実物は、イエス・キリストです。聖所と至聖所とを仕切っていた大きく分厚い垂れ幕は、キリストの肉体を象徴していたのです。
神とお会いできる新しい生ける道が、主イエスの十字架の御業によって、開かれたのです。福音書記者たちが記しているあの出来事です。「イエスは再び大声で叫んで霊を渡された。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。」(マタイ27:50〜51)。神と人間との仲介者は、すべてにおいて有限で罪ある人間の大祭司ではなく、イエスという永遠の大祭司、私たちに同情できる大祭司です。
さらに22節では、幕屋礼拝で使用された儀式における血と水が描かれています。そのイメージをもって、「心には血が振りかけられて」いるし、「からだ」は「きよい水で洗われ」ていると言います。身も心も神は私たちをきよめ、赦し、受け入れてくださっているということです。すべては、イエス・キリストということです。
3,神に近づくことは、どのような行いを生み出すか
希望を告白し続ける
23節も見ましょう。「神に近づく」ということは、実際にどのような行為、行動として表されていくものなのかを明らかにしています。第一は、23節の「希望を告白し続ける」です。希望することができなければ、信仰を持てないということではありません。信仰を持っているなら希望を持つことができるという結果を教えています。信仰を持ちつつ、失望し続けることはできません。信仰はいつも私たちのうちに希望の一筋の光を投じてくれるのです。また、ここは直訳では「希望の告白を堅く保とう」です。私たちがいただいている信仰の内容、イエス・キリストは「希望の告白」そのものです。
愛と善行へと刺激し合う
24節には、第二の「神に近づく」ことの行動の現れとして、「愛と善行を促すために、互いに注意を払う」ことが示されます。「促す」と訳されたことばのギリシア語は「刺激する」(パロクスースモス)という意味のことばです。また、「注意を払う」も、「考えながら見る」というのが原意です。ですので、それらのニュアンスを踏まえると、「愛と良い行いへと刺激するために、お互いのことをよく考えながら見ていこう」という意味となります。こういうところを読むと、ある学者がヘブル書の著者はたいへん優れた牧会者であると評していたことがよくわかります。私たちの教会もすべての活動が、互いを愛と良い行いへと刺激するものでありたいと思います。そのようにして私たちは神に近づいていきます。
集まって励まし合う
最後に25節です。ここでは、集まることの重要性、空間と時間を共有すること、集まって礼拝することの明確な意義が語られています。集まることの大きな理由は「励まし合う」ためです。この「励まし合う」ことで、信仰の共同体意識、神の御前で一つとなる喜びが生まれます。この「励ます」と訳されたことばも、直接的には「声をかける」、「呼びかける」ということばです。神に近づく私たちに対して、著者は呼びかけます。「さあ、礼拝に集いましょう」と。