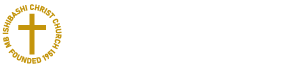ヘブル人への手紙 11:32ー40
礼拝メッセージ 2025.10.5 日曜礼拝 牧師:船橋 誠
1,決断する信仰(モーセの信仰から)
信仰の道を選び取る
「信仰の章」と呼ばれるヘブル人への手紙11章を続けてみていますが、読めば読むほど、信仰というものがいかに大きなものであるのかを感じます。アベル、ノア、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセなど、彼らの信仰による生き方が凝縮されて述べられ、「この人物は信仰によってこんな生き方をしたのだな」と、数々のことが教えられます。これらの内容は「信仰の生き方」の見本(サンプル)であり、「信仰の図鑑」として見ることもできます。
今回は、モーセとその他の信仰者たちについて見ていきたいと思います。ここに記されているモーセの信仰は、一言で言い表せば、「決断する信仰」と呼ぶことができるでしょう(23〜29節)。24節「信仰によって、モーセは…ファラオの娘の息子と呼ばれることを拒み、…神の民とともに苦しむことを選び取りました。」と記されています。モーセは、「信仰によって、…拒み、…選び取りました」。27節「信仰によって、彼は…エジプトを立ち去りました」。28節には彼が信仰によって、神により命じられたとおり、過越の儀式を捧げたことが記されています。モーセは信仰によって神の道を選び取ったのでした。
私たちの人生は決断の連続です。その決断の積み重ねとそれによって生じた結果が「今」に結びついています。軽微に思えるような決断もあれば、長い時間をかけて慎重に決断しなければならない重大なものもあります。モーセの信仰による決断は、彼にとっても、また神の民の歴史にとっても、非常に大きく重要な決定となりました。
捨てる(拒む)という決断
ここで、彼の決断する信仰は、「拒む」という態度で表されています。つまり、「捨てる」ことです。彼は信仰ゆえに、世の栄誉、快楽、富を捨てました。24節では、成人したモーセが、ファラオの娘の息子という栄誉、その大きな地位を捨てたのです。モーセは四十年間、当時最も繁栄し、最新の文明社会であったエジプトで、王子としての身分を持っていました。極めて快適な生活を彼が享受していたことは間違いないでしょう。最高の食事、最高の住居、最高の娯楽など、その時代が提供しうるあらゆる最高のものを受けていたと思います。彼は最高のエジプト人として生きていくこともできる中、虐げられているイスラエルの民と苦しみをともにして生きる道を選び取ったのです。
モーセはどのようなにこれらの決断に進んだのでしょうか。ヘブル書は彼が見ていたものを伝えています。26節と27節です。「与えられる報いから目を離さなかった」と記されています。それは彼の中でエジプトの富が霞んでしまうほどの驚くべき光を放っていました。キリストが地上に来られる千四百年以上前に、モーセは民を罪から救ってくださるメシアなるお方のことを神からの啓示を通して知っていたと思います。27節には「目に見えない方を見ているようにして」という、信仰の本質を示す表現が述べられています。まさに「信仰は、…目に見えないものを確信させるもの」(1節)です。
2,勇気ある信仰(その他の人々の信仰から)
勇気の源である信仰
32節以降に移りましょう。「これ以上、何を言いましょうか。」と著者は記します。「ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても語れば、時間が足りないでしょう」。その通りで、ほかの人物についても一つ一つ記すなら、それはきりがないというわけです。それでまとめて33節から38節の記述があります。その内容を見れば、これらの人々が、どんな信仰に生きたかと考えると、それは「勇気ある信仰」と言えば良いでしょうか。33節と34節を見ると、「国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを手に入れ、獅子の口をふさぎ、火の勢いを消し、…」と書いています。これらの人たちはその人生において、戦いや試練に直面していたことがわかります。彼らは元々強かったわけではなく、むしろ信仰ゆえに彼らは「弱い者なのに強くされ」たのです。これが信仰の力というものです。信仰によって与えられた勇気です。勇気の源は信仰です。
闘いに耐え抜く信仰
「獅子の口をふさぎ、火の勢いを消し」というのは、ダニエル書に記されたダニエルのことや、シャデラク、メシャク、アベデ・ネゴのことです。これらのことは彼らに勇気があったからできたことではなく、彼らに与えられた信仰がそうさせたのだということです。すべては「信仰によって」なのです。35節後半から38節にかけての記述は、たいへん重苦しい内容です。ここには十数種の迫害の手段が挙げられています。この世の見方からすれば、信仰を持つことのマイナス面に思えるかもしれません。
たとえば、35節に「拷問」ということばがあります。これは新約聖書でここだけにしか出て来ない単語(ギリシア語:トゥンパニゾー)です。それは打楽器のティンパニーの語源になりましたが、ここの意味は、人を大きな円筒状の回転する道具に縛り付けて、棍棒で殴打し続けるという残虐な刑罰方法のことです。また彼らは、むちで打たれ、牢屋で鎖につながれたりしました。「石で打たれる」のは、ユダヤ人の間で行われた酷い死刑方法でした。「のこぎりで引かれる」とは、伝承によると預言者イザヤがそのようにして殺されたということです。
35節以降の記述は、当時の迫害下にあったヘブル書の読者たちの状況を踏まえたものだったでしょう。あなたがたの今の苦しみは、旧約聖徒たちも通ってきたことであると著者は語っています。そしてその信仰ゆえの苦しみが読者である人たちと聖書とをつなげます。
彼らがそれらの事態に忍耐できた理由は、「目に見えない方を見て」いたからでしょうし(27節)、未来の「もっとすぐれたもの」(16、40節)を得ることになると知っていたからでしょう。
39節と40節はまとめです。けれども、これら旧約聖徒たちは約束されたものを手に入れることはなかったと。なぜなら、神は「もっとすぐれたもの」を用意されていたので、「私たちを抜きにして」、彼らが全うされることはないという驚くべき真理です。それは、キリストによる新しい契約の成就と祝福を彼らは経験できなかったということです。彼らはキリストの来臨と、その後誕生するキリストにある信仰の共同体(教会)を待ち望んでいたが、それを味わうことはできなかったのです。
先取りになりますが、結論は次のとおりです。これら信仰によって生きた聖徒たちのことを思い、「私たちも、一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競走を、忍耐をもって走り続けようではありませんか。…イエスから目を離さずに…」(12:1〜2)。