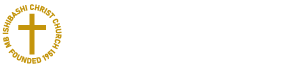ヘブル人への手紙 11:8ー16
礼拝メッセージ 2025.9.7 日曜礼拝 牧師:船橋 誠
1,「信仰によって」ということばが語りかけること
読めば読むほど、この「信仰によって」というみことばは、たいへんインパクトのある語りかけであると感じます。「信仰を持っていた」ではなく、ここで言われているのは「信仰によって、何々をした」ということです。つまり、「信仰によって」でなければ、あり得ない行動を取ったり、人生の重要な選択をしたという人たちのことが記されています。いくつか例を挙げると、「信仰によって、アベルは…すぐれたいけにえを神に献げました」(4節)。「信仰によって、ノアは…箱舟を造りました」(7節)。「信仰によって、アブラハムは…どこへ行くのか知らずに出て行きました」(8節)。「信仰によって、モーセは…神の民とともに苦しむことを選び取りました」(24〜25節)。「信仰によって、…。信仰によって、…。」という繰り返しが、心に重く響いて来るような気がします。それはあたかもこう語りかけているようです。「信仰によって生きたこれらの人たちの足跡に従って、あなたも生きませんか」。あるいは、「信仰によって生きた人々がこのように雲のように証人としてあなたを取り巻いており(12:1)、そしてあなたのことを見ています。それで、あなたは今、何によって生きているのですか」と。
2,信仰によって箱舟を造ったノア
目に見えないものを確信したノア
7節に「信仰によって、ノアはまだ見ていない事柄について神からの警告を受けたときに、恐れかしこんで家族の救いのために箱舟を造り、…」とあります。この「まだ見ていない(事柄)」というのは、ノアだけでなく、この「信仰によって」ということを考えるときに、最も重要なキーワードの一つです。1節に「信仰は…目に見えないものを確信させる」とありました。信仰の道は、まさに目に見えない道であり、その見えないことに人生の基盤を置く生き方にほかなりません。たとえば、私たちのうちで、神さまをその目で見たことはないでしょうし、キリストも、聖霊も、天の御国を見た人もいないと思います。しかし、見てはいないが、信じているし、それを基盤に生きるのが、信仰の事実です。ペテロが言うように、その結果を確認できるのです。「あなたがたはイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見ていないけれども信じており、ことばに尽くせない、栄えに満ちた喜びに躍っています。」(Ⅰペテロ1:8)。ノアは目には見えない神からの語りかけを聞きました。「すべての肉なるものの終わりが、来ようとしている。…あなたは自分のために、ゴフェルの木で箱舟を造りなさい」と(創世記6:13〜14)。こうも言われました。「あと七日たつと、わたしは、地の上に四十日四十夜、雨を降らせ、わたしが造ったすべての生けるものを大地の面から消し去る」(同7:4)。
箱舟の建造という途方もない事業
明確なことはわかりませんが、創世記2章5節にあるように、地上に雨が降ったことのない状態がこの世界に続いていたとしたら、ノアは「雨が降る」と聞かされても、雨自体を見たことがなかったのかもしれません。また、ノアは主から命じられたとおり、巨大な箱舟を陸地で建造したのです。舟はたいへんな大きさのもので、長さ132メートル、幅22メートル、高さ13メートルもありました。設計図はあったのでしょうか。造船技術をどこで得たのでしょうか。ノアとその家族だけでそんな巨大なものを造れるものでしょうか。いずれにしても途方もないことだったに違いありません。創世記5章32節にノアの年齢が「五百歳」とあり、ノアが「六百歳」のときに洪水が起こったことが記されているので、この箱舟を造るのに百年かかったのかもしれません。ノアがしたことは、想像することさえ難しいような行動です。ヘブル書が続けて記していることは、ノアが信仰によって歩んだ日々、その生き方は「世を罪ありとし、信仰による義を受け継ぐ者と」したということです(7節)。当時ノアたち以外にも多くの人間がいたと思いますが、ノアのことばをまともに聞く人はいなかったのでしょう。しかし、ノアは信仰によって、救いのために、コツコツと毎日、箱舟を造り続けたのです。
3,信仰によって旅人となったアブラハム
約束を信じたアブラハム
さて、次にアブラハムについて見ていきましょう。ここで述べられているアブラハムに対する神の約束はおもに二つです。一つは8節から10節の相続地を与える約束です。もう一つは子孫が与えられるという約束です。創世記12章です。「『あなたは、あなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、わたしが示す地へ行きなさい。そうすれば、わたしはあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、…。』アブラムは、主が告げられたとおりに出かけて行った。」(創世記12:1〜4抜粋)。アブラハムの一族は、最初カルデヤ人の地ウルに住んでいました。そこからハランへ移り、そしてカナンの地に住むことになりました。これは、彼がいろいろと調べて準備した移住計画ではなく、それがどんな場所であるのか何も知らないまま、ただ神に呼び出されて、旅立ったのでした。しかも、彼らはそこが相続地として導かれたはずなのに、その土地を所有することはなかったのです。彼らは定住者ではなく、「他国人のようにして住み、…天幕生活を」しました。アブラハムが生前取得したのは、妻サラを葬るための僅かな土地だけでした。
もっと良い故郷を求めていたアブラハム
11節と12節は子孫が与えられる約束です。サラは不妊で苦しみ、後を継ぐ子孫が生まれず、歳月ばかりが過ぎていくという落胆と諦めの中で、神は子をサラの胎に宿すようにされました。年齢的に妊娠や出産ができることは考えられない状況でしたが、息子イサクが与えられたのです。「天の星のように、海辺の数え切れない砂のように」(12節)とあるように、そのイサクからヤコブが生まれ、やがてヤコブ一族がエジプトで増え、そこを脱出して約束の地に入る時には、他国人でも寄留者でもなく、定住者として入国することになりました。けれども、ヘブル書がここで語っているように、旧約の聖徒たちにとって約束の地である地上のカナンは、彼らの真の故郷ではなかったのです。16節「しかし実際には、彼らが憧れていたのは、もっと良い故郷、すなわち天の故郷でした」。この後、この書が語るのは、もっと先にある未来の都のことです。13章14節に「私たちは、いつまでも続く都をこの地上に持っているのではなく、むしろ来たるべき都を求めているのです」と言われています。信仰はこのように終末的未来へと、私たちの心の目を向けさせます。今、目で見ているものを超えて、そしてこれから起こって来る出来事を超えて、さらにその先へと、神は私たちを連れ出されるのです。