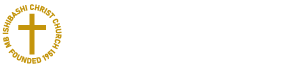ヘブル人への手紙 11:1ー7
礼拝メッセージ 2025.8.31 日曜礼拝 牧師:船橋 誠
1,信仰と希望は神にかかっている
ヘブル人への手紙11章は、「信仰によって」が繰り返され、信仰について教えているということで、「信仰の章」と呼ばれています。また、多くの旧約聖書の信仰者たちのことが描かれているので、「信仰の勇者たちの章」といった呼ばれ方をすることもあります。キリスト者にとって、また神を求めている方にとって、最も大切なことはこの「信仰」です。
ただ、誤解を恐れずに言えば、「信仰」そのものが尊いわけではないと思います。信仰心の強さとか、人間の側の一種の能力として、強い信仰を持ちましょう、信仰力を鍛えましょう、というのが、聖書が語っているメッセージではないということです。ペテロは書いています。「あなたがたは、キリストを死者の中からよみがえらせて栄光を与えられた神を、キリストによって信じる者です。ですから、あなたがたの信仰と希望は神にかかっています」(Ⅰペテロ1:21)。大事なのは、「キリストを死者の中からよみがえらせ…栄光」を与えた「神」です。人間の信仰が神を動かしたわけではないのです。
ですから、「信仰」というものを、「信頼」と言い換えたほうが良いのかもしれません。それは小さな子どもが保護者の手を握るようなものです。別に、子どもが保護者に頼ることを「すごい」とはあまり思わないでしょう。その子どもの信頼する心に応えて、子どもを守るのは保護者です。でも、頼ってもらわないと、保護者は喜ばないでしょうし、助けることができないこともあるのです。
2,信仰は望んでいることの実体である
「信仰は、望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです」。新改訳聖書では脚注に別訳を載せています。そこに、「…の実体であり」と書いています。本文のほうの「…を保証し」と訳されたことばは、ヒュポスタシスというギリシア語の名詞であり、本来「実体」、「実質」、「本質」という意味を持っています(1:3参照)。「信仰とは、希望することの実体である」ということです。少しわかりにくいかもしれませんが、言い換えると、信仰は確かな希望に直接結びついているものであって、それは何か人間の側の願望や幻想のように形のないものではなく、実質のあるものだということです。ここで著者が言おうとしていることは、信仰というものは、人間の主観的な思い込みではないことを示しています。むしろ、それは客観的事実に基づいているものです。このヒュポスタシスには、「権利証書」の意味があります。確かに信仰は希望がまだ実現していなくてもその権利証書を手にしているのと同じ役割をするのです。
3,信仰はこの世界の見方を変える
その信仰による霊的な現実に基礎を置いて、これまで生きてきた多くの見本がある、と2節で著者は言います。3節では、創世記1章の天地創造のことが言われているようですが、これは、信仰というのは、この世界、いや地球の見え方さえも変えてしまうということです。その世界観や生きる意味や目的について、私たちの視点を根底からガラッと変えるのが信仰です。著者が「信仰によって」という語り出しを、天地創造のことから始めているのは、これが信仰によって生きる人たちのあらゆる経験や出来事の見る方法に繋がっているからです。
この目に見える世界は、同じく目に見える材料から偶然に生じてできたものではなく、神の力によって、神のみことばによって、存在へと呼び出されました。目に見えない「神」によって、そして同じく目に見えない「神のことば」によって、この世界は成り立っているのです。私たちが踏みしめることのできるこの大地、見上げることのできる空、この空間と時間もすべて、そして私たち自身も、見えない神が、見えないことばで、造り出されたものです。
4,信仰によって献げ、移される
4節から38節まで、信仰をもって生きた人々の実例が挙げられていきます。4節ではアベル、5節と6節でエノク、7節はノアです。アベルが信仰者の最初の実例として選ばれていることは興味深いことです。アダムやエバではなく、最初にアベルです。アベルについての創世記の登場場面はたいへん短く(同4:2〜8)、そしてその命も儚く終わった人でした。主は兄カインのささげ物に目を留められず、弟アベルのささげ物に目を留められ、それがカインの殺人の動機となりました。創世記には神が好まれた理由が明確には示されていませんが、ヘブル書には神にとって「良いささげ物」だったと述べられています。
次に挙げられているのは、エノク(創世記5:18〜24)です。エノクも系図的な記事の中で短く記述されている人物です。創世記5章を最初から読むと、系図上挙げられている人々の生きた年数と比較すれば、短い生涯であったことがわかります。彼については出来事は何も記されず、彼が「神とともに歩んだ」こと、そして「神が彼を取られた」ということだけです。
彼らのことで共通していることは、「死」ということです。4節でアベルについて「彼は死にましたが」とあり、5節ではエノクについて「死を見ることがないように移されました」とあります。詳細なことはわかりませんが、突然いなくなった、あるいは死を迎えたのがこの二人に共通していることです。人間的に見るならば、短い生涯で、突然地上からいなくなった彼らは、不幸な人々に見えたのかもしれません。けれども、著者は言うのです。「信仰によって、アベルは…すぐれたいけにえを献げ」、「信仰によって、エノクは…移された」と。つまり、信仰によって彼らは生きたし、信仰によって彼らは死んだのだということです。
5,信仰は未来へと繋がっている
彼らは地上で「約束のものを手に入れることはありませんでしたが」(13、39節)、「神は、もっとすぐれたものを用意して」(40節)おられるのです。ワード聖書注解のウィリアム・レインは、こう記しています。「信仰とは、このように未来に向けられた実際に効力のあることである。それは生ける神と直接的で個人的な出会いから湧き出てくる。信仰による前向きな能力は、神のことばを支えとして、信仰者が勇気と平安をもって、目に見えない未来へと踏み出していくことを可能にするのである。…」。6節には信仰について重要な宣言があります。「信仰がなければ、神に喜ばれることはできません」。信仰は、あってもなくても良いものではありません。なくてはならないものです。なぜなら、信仰がなかったならば、神に喜ばれることは決してないからです。