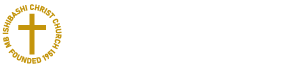ヘブル人への手紙 10:26ー39
礼拝メッセージ 2025.8.10 日曜礼拝 牧師:船橋 誠
1,背教者とならないように注意しよう(26〜31節)
苛烈さを増す警告
ここまで何度か警告と励ましのことばを熱心に語ってきた著者ですが、11章の「信仰の章」、「信仰によって…」で始まる内容に入る前に、ここでまた、新たに同様のことを記しています。神は愛と恵みに溢れた優しいお方でありますが、著者は今回の箇所においては、義なる方として正しくさばかれることをまっすぐに教えています。警告のことばはこれまでにもありましたが、著者はさらに厳しく、苛烈な表現で神のさばきを示して、読者一人ひとりに警告を発しています。「逆らう者たちを焼き尽くす激しい火」(27節)、「あわれみを受けることなく死ぬ」(28節)、「いかに重い処罰に値するか」(29節)、「主は御民をさばかれる」(30節)、「生ける神の手の中に陥ることは恐ろしい」(31節)と、畳み掛けるように述べています。
初めの契約であるモーセの律法でも違反者は厳しくさばかれたのだから、新しい契約を汚れたものとするなら、もっと恐ろしいさばきがあるはずで、それが一体どんな厳罰となるのか、よーく覚えておきなさいと、言われています。これを読むと、一般的に、旧約聖書は厳しく、新約聖書は優しい、というような捉え方は、間違っていることがわかります。ヘブル書の著者はむしろ逆だと言っています。
この警告をどのように見るべきか
このような警告をどう受け止めるべきでしょうか。過去から、この警告のことばは、誰に、そして何を語っているのか、真剣に考えられてきました。3世紀から4世紀にかけて、一部の人々は、この警告が洗礼を受けた後、大きな罪を犯したすべての人に当てはまるのではないかと考え、洗礼を受けることを可能な限り人生の最後の瞬間まで延ばすというようなことをしていたそうです。人生の途上で罪を犯して、救いを失ってしまいたくないと思ったからです。しかし、その理解も洗礼を遅らせたことも正しいあり方ではありませんでした。他方、6章やこの箇所に描かれているのは、特別に悪い人たちのことであって、これは例外的な事例であると考えた人たちもいました。
いずれにせよ、過去のある人たちのように、洗礼を遅らせようとしたり、逆に警告を自分と無関係とする見方も、どちらもこの箇所への適切な応答とは言えません。それでは、どう受け止めることが必要なのでしょうか。まず、この警告は自分事として受け止めることが必要です。26節は「もし私たちが」で始まっています。つまり、ここで言われている警告は、このヘブル書の著者や読者たちのすべてが、さばきを受けるような背教者となる危険性を持っているということです。
悔い改め不可能とは?
しかし、また「進んで罪にとどまり続けている」と書いていることにも注意が必要です。私たちの信仰が弱くなって、罪を犯したり、不従順になることがあります。これは確かに良くないことですが、それでも、私たちはなんとか信仰に立ち続けようとして、葛藤しながら、悔い改めて、神に従おうと努めます。そのように罪に負けることがたとえ何度あったとしても、そこから神を求めていこうとしているのなら、「進んで罪にとどまり続ける」ことにはおそらくならないでしょう。しかし、もし神に従うことをあきらめ、信じてきた方を否定して、信仰そのものを捨てようとしているのなら、この26節から31節に書かれている方向に進んでしまう可能性を否定できません。
29節には「神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の血を汚れたものと見なし、恵みの御霊を侮る者」だとありますから、罪に対して鈍くなって良心が麻痺し、聖書が語る信仰を否定して、不要なゴミのように扱うならば、もはや悔い改めが不可能となるのかもしれません。ここで語られている状況の人のことを、いくつかの英語の解説書では、それゆえ「背教者」(英語アポステイト)と呼んでいます。背教者とは、意図的で完全な信仰の離反や離脱、あるいは信仰を捨てて反対者の側に立った人のことです。有名な聖書学者F.F.ブルースが注解書にこう書いていました。「神ご自身は、悔い改めるすべての人を赦すと堅く約束されているが、人々はもはや悔い改め不可能な心と生活の状態にまで達し得ることを、聖書も経験も同様に示唆している。」(『ヘブル人への手紙』宮村武夫訳 聖書図書刊行会)と。
しかし同時に、聖書学者ゼーン・ホッジズは6章と10章のさばきの記述が、最終的な神のさばき、いわゆる地獄のことを述べておらず、その人の生涯に起こる神からの報い、懲らしめであると言います。そうなのかもしれません。たとえば、31節の「神の手の中に陥る」という表現は、ダビデが罪を犯した時、「私を主の手に陥らせてください」(Ⅰ歴代21:13)と言って、むしろそれを選択しています。ヘブル書のこの記述は、それを踏まえてのことばとされています。
大切な点は、神の恵みや愛を自分勝手に誤解して、軽んじたり、侮ったりせずに、神を正しく恐れる心を忘れてしまわないように注意することです。ヘブル書や他の聖書の警告的な文章は、私たち現代人が忘れがちな、生ける神の圧倒的な御力、絶対的な支配、悪を1ミリも許さない完璧な正しさを、私たちに思い起こさせるものです。
2,信じていのちを保つ者となろう(32〜39節)
信仰の日々を思い起こす
著者は32節で「初めの日々を思い起こしなさい」と言っています。信仰をもって生きる中で、楽しいこともありますが、いろいろな苦しみや痛みを経験することもあります。32節から34節を見ると、本書の宛先の人々は、信仰ゆえの犠牲や迫害を味わったのでしょう。信仰の歩みをしていくことの中で、いろいろな労苦や困難なところを通ります。しかし、そうした経験がかえって、信仰の財産になることもあります。それらのことを振り返るとき、大変だったけれども、それで今の私があるんだと確認ができます。また、私の理解では、ここで語られている過去の日々を思い起こすというのは、著者自身が11章以降で展開していくように、過去の信仰者たちのこと、そして歴史にも思いを馳せることが含まれていると思います(参照;11章および13:7)。
主の来臨の約束と大きな報い
過去を思い返すことと同時に、35節以降にあるように、私たちは未来にもしっかりと目を向けましょう。それは「大きな報い」(35節)であり、神の「約束のもの」(36節)です。著者はパウロがしたように、ハバクク書のことばを引用しています(37−38節)。主の来臨は必ずあり、それは遅れません。信仰を持つ者に約束された報いがどれほど素晴らしく、比類なく、優れているのか、聖書の語るところを学んでいく必要があります。それゆえ信仰の確信を投げ捨ててはならないのです。